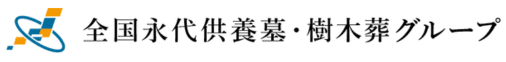無縁仏とは?原因や問題点、無縁仏にならないための対策について徹底解説
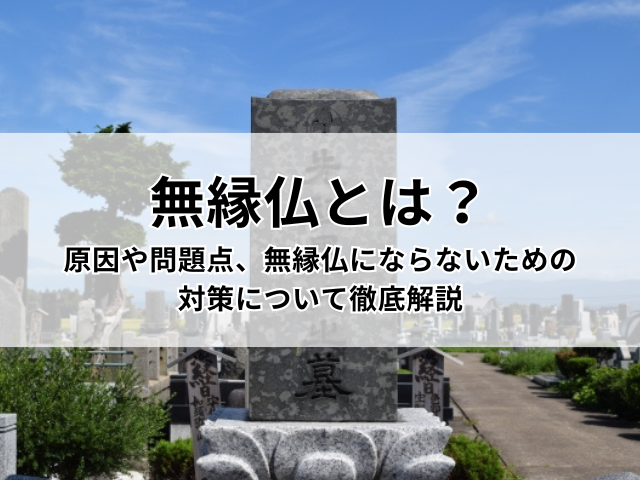
無縁仏とは、本来供養をしてくれるはずの親族や近しい間柄の方がいなくなり、遺骨やお墓が放置された状態のことを指します。
近年は少子化や核家族化の影響により、無縁仏は増加傾向にあります。親族がいても、お墓が遠方にあることで管理が行き届かず、結果的に無縁仏となってしまうケースも少なくありません。また、自分の死後にお墓を守る人がいなくなる場合も、同様に無縁仏となる可能性があります。
この記事では、もしお墓が無縁仏になってしまったときの対応方法や、そうならないために事前にできる対策について解説します。

無縁仏とは?

まずはじめに、「無縁仏とは何か」について説明します。
無縁仏の基本的な意味合いを抑えましょう。
無縁仏の基本的な意味
お葬式や供養をする親族や親しい友人がいなくなった故人の遺骨やお墓のことを「無縁仏」といいます。
下記は無縁仏となる主なケースです。
- 遺族や近しい関係者がいない。供養する人がいなくなった場合
- お墓参りや管理が行われず、お墓が荒れた状態になっている
- 火葬後に遺骨の引き取り先がない
お墓参りに行った際、放置され荒れてしまったお墓を見かけることがあると思いますが、そのようなお墓は無縁仏になっている可能性があります。
無縁仏と無縁墓の違い
無縁仏とよく似た言葉に「無縁墓」があります。両者はほぼ同様の意味合いを持ちますが、若干ニュアンスが異なるため、定義を整理しておきましょう。
- 無縁仏:本来は供養をしてくれる家族や縁者がいなくなった故人、またはその遺骨やお墓を指す。「人」と「その人のお墓」両方を含む広い意味合いで使用される。
- 無縁墓:お墓そのものを指す。長年お墓参りがされなかったり、管理されず、草木に覆われたり、石が風化して荒れてしまった状態のお墓を指す。
供養する人がいなくなった故人やそのお墓は「無縁仏」と定義され、「無縁墓」はお墓そのものを指すと考えることができます。

無縁仏になる原因

現代社会では、少子高齢化や都市部への人口集中に伴い、やむを得ず無縁仏になってしまうケースもあります。
この章では、無縁仏になってしまう主な原因について解説します。
供養してくれる身内がいない
供養してくれる身内がいない場合、無縁仏になる可能性があります。
近年では、親族との交流が「核家族化の進行」や「都市部への人口集中」に伴う地理的な距離により途絶えている場合、親族同士のつながりが薄くなるケースもあります。その場合、供養の担い手がいなくなり、お墓が放置されて無縁仏となってしまうことがあります。
お墓の後継者がいない
お墓を継ぐ後継者がいないことも、無縁仏となる大きな要因です。
少子化や未婚化の影響で、子どもや跡継ぎのいない家庭が増加しています。その結果、将来的にお墓を守る人がいなくなってしまい無縁仏になる可能性があります。
管理費が支払えない
一般的なお墓を維持するには、寺院や霊園に対して毎年「管理費」を支払う必要があります。
ところが、
- お墓の後継者がいない
- 継承者がいても経済的な事情などから管理費が滞納された
このような場合、寺院や霊園から「無縁仏」と判断され、最終的にお墓が撤去されてしまうことがあります。
その際、遺骨は無縁塚や共同墓へと移され、後から取り出すことはできません。
家族や親族がいる場合でも、管理費の支払いが滞れば無縁仏とされてしまう可能性があります。
お墓が用意されていない
一般的には、故人が亡くなると家族や親族が中心となってお墓を用意し、納骨を行います。しかし、故人に家族や親族がいない場合や経済的な事情によりお墓を建てることができない場合、結果的に無縁仏となってしまうことがあります。
無縁仏になるとどうなるのか

この章では、もし無縁仏になった場合どうなるかという点について解説します。
無縁死の場合
無縁死とは、家族や縁者がおらず、社会から孤立してしまった状態で死亡する場合のことです。
無縁死してしまい、引き取り手がいない遺骨への対応は法律で定められています。
身元不明の遺体は「行旅死亡人(こうりょしぼうにん)」と呼ばれ、その所在地の自治体が状況や容貌、遺留品などを記録した上で埋葬を行います。多くの場合は火葬後、一定期間自治体で遺骨を保管し、その後は合祀される流れになります。
お墓の後継者がいない場合
お墓を引き継ぐ人がいない場合や管理料が滞納された場合や放置されている場合、そのお墓は霊園の管理者により「改葬」されます。
1999年3月の墓埋法改正により、管理料が支払われていないお墓については以下の流れが定められました。
- 管理者が、埋葬されている故人や管理者の氏名・本籍などを官報で告示する
- お墓に「無縁墓になる可能性がある」旨を記した立て札を設置する
- 1年間申し出がなければ、無縁墓として処分できる
処分されたお墓は整地され、遺骨は合祀されたうえで、別の家のお墓が建てられることになります。
遺骨を後から引き取ることは可能か
無縁仏となった遺骨は、一定期間を過ぎても引き取り手が現れなければ、最終的に合祀されるのが一般的です。
合祀とは、骨壺から遺骨を取り出し、他の遺骨と一緒に埋葬する方法です。一度合祀されると、特定の個人の遺骨を取り出すことはほぼ不可能です。そのため、後になって遺族間でトラブルに発展するケースもあります。
また、合祀の場合他の遺骨と自分の遺骨が混ざること自体に抵抗がある方も多いです。 いらっしゃいます。
宗教上の問題
ここまで無縁仏になってしまった場合の手続き上の問題について言及してきましたが、最後に宗教上の問題について簡単に解説します。
無縁仏は「十分に供養されていないために心残りを抱えている」といわれることがあります。供養してくれる人がいないということは、お供えや祈りを受けられないということでもあります。
生きている人にたとえるなら、食事や水が与えられず、常に満たされない状態にあるようなものです。そのため、無縁仏は寂しさや悲しみを抱え、気持ちが不安定になると考えられています。
昔からの言い伝えでは、そのような無縁仏の思いが周囲の人に影響を及ぼすこともあるとされており、きちんと供養をすることの大切さが語り継がれてきました。
第三者に迷惑がかかってしまう場合がある
無縁仏になり、遺骨の引き取り手がいない場合、寺院や霊園などの第三者に負担をかけてしまう可能性が考えられます。
無縁仏になり、改葬が必要になるケースですが、これらの手続き上の処理は霊園管理者が行います。
霊園管理者は主に自治体(行政)や寺院が該当しますが、自治体が処理する場合、改葬費用は税金から負担されます。また、寺院が改葬する場合も寺院側にお金を負担させ手間をかけてしまう結果につながります。
このようなことを考えても、できるだけ無縁仏になる状況は避けたいところです。
では「どうしたら無縁仏にならずに済むのか」について次章で解説していきます。
無縁仏にならないための対策

最後に無縁仏にならないための対策について説明します。
永代供養や合祀墓を利用する
1つ目の方法は永代供養墓や合祀墓を利用し永代供養を行う方法です。
永代供養とは、遺族や子孫に代わり、霊園や寺院が遺骨の管理をしてくれる供養方法のことをいいます。
お墓のお手入れやお墓参りをする方がいない方でも、遺骨を護ってもらえることが永代供養の大きな特徴です。
・合祀、合葬墓(石材型)
合祀や合葬墓は、予算の少ない方や身寄りのない方の遺骨に適していますが、他人の遺骨と混ざり合う埋葬方法のため、気になる場合は別の永代供養墓を選びましょう。
・集合墓(石材型)
集合墓は骨壷や骨箱をまとめて陳列して保管する設備のため比較的安価ですが、手を合わせる対象が不明瞭なことやお参りでの混雑、一定期間後は合祀されることに注意が必要です。
・個別安置墓(石材型)
個別安置墓は申し込み単位で仕切られているため対面してお参りできる永代供養墓です。一定期間後に合祀する以外にも、合祀しないタイプや大人数が納骨できるケースや管理費不要の場合もあります。
永代供養墓の中でも、個室のように仕切られているため、より一般的なお墓に近い形式であるといえます。
| 種類 | 費用 |
| 合祀・合葬墓 | 約5~30万円 |
| 集合墓 | 約20~50万円 |
| 個別安置墓 | 約50~120万円 |
当サイトで紹介させていただいている永代供養墓は、供養はもちろん、管理面も充実した寺院・霊園を厳選しております。特に、永代供養墓「燈」は、永代供養でありながら、個別で仕切られている形式のマンションタイプのお墓です。
永代供養墓をご検討の方は是非一度ご検討ください。

墓じまいを生前に行う
墓じまいとは、墓石を撤去して墓地を更地に戻し、管理者に返還することを指します。
無縁仏になる原因のひとつに、お墓の管理者がいなくなることがあります。そのため、将来的にお墓を管理してくれる子どもや親族がいない場合は、自身が入る予定のお墓を生前に墓じまいするという方法も、有効な選択肢のひとつです。
ただし、墓じまいを行う際には、近親者に事前に相談し、了承を得ておくことを忘れないようにしましょう。
死後の手続きを委託しておく
死後に遺骨の管理を任せられる家族や親族がいない場合は、死後の手続きを友人や知人に依頼する方法もあります。
その際には、死後事務委任契約を結ぶことで、「遺品の整理」「葬儀や埋葬の手続き」「お墓の管理」などを任せることができます。
また、エンディングノートを用意しておく方法も有効です。
まとめ

近年は、供養や管理が行われず放置されている「無縁仏」が増えており、社会問題のひとつとなっています。
無縁仏になると、お墓は撤去され、遺骨は合祀されるため、後から遺骨を取り出すことはできなくなってしまいます。
無縁仏になってしまう状態を防ぐためには、永代供養のお墓に改葬したり、事前に墓じまいをするなどの対策が有効です。
お墓についてお悩みの方は、是非当社が提携する寺院・霊園へ一度ご相談ください。
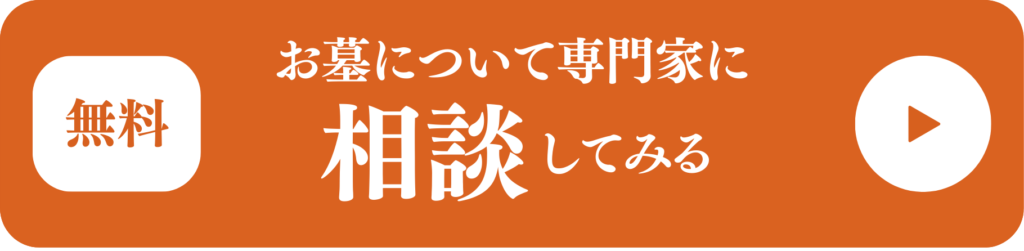
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です