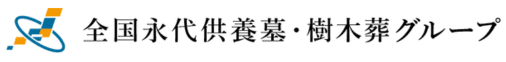離壇とは?離壇の進め方やトラブル対策、お寺の本音まで解説
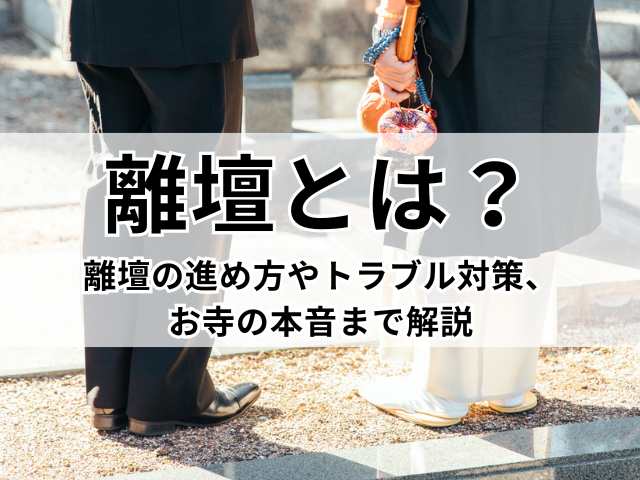
近年、これまであったお墓の維持が困難になり、墓石を撤去する墓じまいを検討する人が増えています。
お墓が寺院にある場合、墓じまいと同時にお寺との檀家の関係を解消する「離壇」する必要があります。
この記事では離壇の意味や手続きの流れ、注意点や費用感、そしてお寺側の本音までを網羅的に紹介します。円満にお墓じまいを進める際は参考にしてください。
↓お墓じまいした後のお墓はこちらから↓

離壇とは?

離壇とは、これまでお世話になってきた寺院との檀家関係を解消することを指します。
お墓じまいは「お墓を片付ける」ことですが、その過程で寺院墓地にお墓がある場合は、離壇の手続きが必要になるケースが多いです。ここでは、檀家制度の背景と、離壇とお墓じまい・改葬の関係について整理します。
檀家制度の概要
日本では江戸時代に「寺請制度」が導入され、すべての人がどこかの寺院に所属し、檀家として戸籍や葬祭を管理されていました。
これが檀家制度の始まりです。現代では義務ではなく、寺院墓地にお墓を持つことで自然と檀家になるケースが一般的です。檀家になると、年会費や寄付、法要の依頼などを通じて寺院との関係を維持します。
しかし近年は、少子化や都市部への移住などで「お墓を継ぐ人がいない」「費用負担が重い」といった理由でお墓じまいを選ぶ人が増えています。その際に必要となるのが、寺院との関係を整理する「離壇」です。
離壇と墓じまい・改葬の関係性
お墓じまいとは、現在あるお墓を撤去して遺骨を取り出すことです。改葬は、その遺骨を新しい納骨先に移すための法的な手続きです。
一方、離壇は「寺院との檀家関係を終了すること」であり、物理的なお墓の撤去や遺骨の移動そのものを意味するわけではありません。
ただし、寺院墓地にお墓がある場合は、お墓じまい・改葬と同時に離壇も発生します。寺院との関係を解消するためには、墓地の使用契約を終了し、遺骨を取り出して別の納骨先へ移す必要があるからです。
つまり、
・離壇=人と寺院の関係を終えること
・お墓じまい=お墓を撤去すること
・改葬=遺骨を新しい場所へ移すこと
というように、それぞれ意味は異なりますが、実際の手続きでは重なり合う部分が多いのです。お墓じまいを検討する際には、離壇や改葬も含めて一連の流れとして考えることが大切です。
離壇が必要になるケース

それでは、具体的に離壇が必要になるケースを紹介します。
改葬する場合
改葬とは、遺骨を現在のお墓から別の墓地や納骨先へ移すことを指します。寺院墓地にお墓がある場合、改葬を行うには寺院との契約を終了する必要があるため、離壇の手続きが不可欠です。
たとえば、都市部に住む子ども世代の近くに遺骨を移すケースや、永代供養墓へ改葬するケースでは、寺院に「離壇証明書」を発行してもらう流れが一般的です。改葬と離壇は切り離せない関係にあるといえるでしょう。
宗派を変える/無宗教にする場合
檀家制度は、特定の宗派や寺院とのつながりを前提としています。そのため、別の宗派に改宗したり、無宗教での供養を希望したりする場合には、現在の寺院との関係を解消する必要があります。
たとえば「仏式からキリスト教式に変えたい」「宗派に縛られず自由な供養を選びたい」といった場合、離壇を経て新しい供養先を選ぶ流れになります。
るでしょう。
遠方で管理が困難になった場合
お墓が実家近くの寺院にあるものの、子ども世代が都市部に移住してしまい、定期的にお墓参りや管理を行うことが難しいケースもあります。
この場合、管理の負担を軽減するためにお墓じまいを行い、永代供養墓や納骨堂へ移すことが検討されます。その際、寺院墓地にお墓がある場合は離壇が必要です。物理的な距離の問題から離壇を選ぶ人は少なくありません。
経済的負担の軽減を目的とする場合
檀家である以上、年会費や寄付、法要の費用など、寺院との関係維持には一定の経済的負担が伴います。特に後継者がいない場合は、この負担が大きな悩みとなります。
離壇を行い、永代供養墓や合祀墓など維持費のかからない供養方法に切り替えることで、将来的な費用負担を大幅に軽減できます。
檀家のメリット

お墓じまいを進める中で離壇を選ぶと、経済的な負担がなくなるなど、いくつかのメリットがあります。ここでは、代表的な利点を取り上げ、離壇を検討する際の参考になるよう整理しました。
年間の檀家料・寄付などの負担軽減
檀家である限り、寺院への年間の檀家料や寄付、法要の際の謝礼など、継続的な費用が発生します。
これらは寺院の維持や活動に必要なものですが、後継者がいない家庭や経済的に余裕のない家庭にとっては大きな負担となることもあります。
墓じまいをして永代供養墓や合祀墓に移行した場合、初期費用のみで済む場合が多く、長期的に見て経済的な安心につながります。
墓参りや管理の利便性向上
寺院墓地が遠方にある場合、定期的なお墓参りや清掃が難しくなることがあります。
離壇をしてお墓じまいを行い、永代供養墓やアクセスの良い霊園に移すことで、墓参りの利便性が大幅に向上します。
また、永代供養墓や納骨堂では寺院や霊園が管理を代行してくれるため、将来世代や親族に負担をかけずに供養を続けられる点も安心です。結果として、家族全体にとって「無理なく続けられる供養の形」を実現できます。
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、檀家義務のない永代供養墓を全国展開しています。気になる寺院がありましたらお気軽にお問い合わせください。

離壇のデメリット

離壇には経済的・生活的なメリットがある一方で、注意しておきたいデメリットも存在します。
お墓じまいや改葬を進める際には、こうした不利益やリスクを理解したうえで判断することが大切です。ここでは代表的な3つのデメリットを解説します。
寺院との関係性が途絶える
離壇を行うと、長年お世話になってきた寺院とのつながりが途絶えます。
これまで法要や供養をお願いしてきた住職や檀家仲間との関係もなくなるため、精神的な寂しさを感じる方も少なくありません。
また、地域社会において寺院が果たしてきた役割を考えると、離壇は単なる契約終了ではなく「人との縁を切る」側面もあることを理解しておく必要があります。
法要や葬儀の相談先がなくなる
檀家である場合、葬儀や年忌法要などの際には、寺院が相談先・依頼先として大きな役割を担ってくれます。離壇をすると、そのような相談窓口がなくなり、自分で新しい僧侶や葬儀社を探す必要が出てきます。
特に急な葬儀の際には、従来のように「すぐにお願いできるお寺」がないため、準備や手配に時間と労力がかかる可能性があります。
無縁仏になるリスク(墓じまいを伴わない場合)
離壇をしても墓じまいを行わずに寺院墓地にお墓を残したままにすると、将来的に管理されない「無縁仏」になるリスクがあります。檀家でなくなった時点で、寺院が継続的に管理する義務はなくなるためです。
無縁仏となった場合、遺骨が合祀墓に移されるなど、家族の意向とは異なる形で供養される可能性もあります。そのため、離壇を検討する際には、必ず墓じまいや改葬とセットで考えることが重要です。
離壇料について

離壇を行う際、多くの寺院では「離壇料(りだんりょう)」と呼ばれるお礼を渡す慣習があります。以下でくわしくみていきましょう。
離壇料の意味
離壇料は、寺院との檀家関係を解消する際に渡す「お礼」のようなものです。
法的に支払い義務があるわけではありませんが、これまでお墓の管理や法要をお願いしてきたことへの感謝を表す意味で渡されます。
金額の多寡よりも「誠意を示す」という姿勢が重視されるため、離壇料は円満に離壇するための大切な要素といえます。
相場感(なし~20万円程度)
離壇料の金額は一律ではなく、寺院の規模や地域性、檀家としての付き合いの長さによって幅があります。一般的には 5~20万円程度 が目安とされることが多いですが、あくまで目安です。寺院によっては「お気持ちで」と言われることもあります。
また、寺院によっては離壇料を受け取っていないところもあります。
支払いタイミングと渡し方
離壇料は、離壇証明書を受け取る前後のタイミングで渡すのが一般的です。
・タイミング:離壇の合意が整った段階、または離壇証明書を受け取る際
・渡し方:新札を用意し、のし袋(表書きは「御礼」「御布施」など)に包んで手渡す
現金を直接渡すのが基本ですが、寺院の意向に合わせることが大切です。
トラブルにならないための事前確認ポイント
離壇料は明確な基準がないため、金額や渡し方をめぐってトラブルになることもあります。円満に進めるためには、以下の点を事前に確認しておきましょう。
・寺院に「離壇料は必要ですか」と率直に相談する
・金額の目安を聞き、無理のない範囲で準備する
・書面やメモでやり取りを残しておく
・不安がある場合は石材店や第三者に相談する
こうした準備をしておくことで、寺院との関係を最後まで良好に保ちながら離壇を進めることができます。
お寺とのトラブルを避けるためのポイントと、お寺の本音

離壇やお墓じまいを進める際、最も気をつけたいのが「お寺との関係性」です。
長年お世話になった寺院とのやり取りを円滑に進めることは、精神的な負担を減らすだけでなく、手続きをスムーズに進めるためにも欠かせません。ここでは、トラブルを避けるための具体的なポイントを整理します。
事前に丁寧な相談に行く(突然の通知は避ける)
離壇やお墓じまいを決めたからといって、いきなり「やめます」と通知するのは避けましょう。突然の一方的な連絡は、寺院側に不信感を与え、不要なトラブルの原因となります。
まずは住職や寺院関係者に直接会い、事情や背景を丁寧に説明することが大切です。誠意を持って相談することで、円満に合意を得られる可能性が高まります。
書面でやり取りを残す
口頭でのやり取りだけでは、後々「言った・言わない」のトラブルにつながることがあります。離壇料の金額や支払い方法、離壇証明書の発行など、重要な内容は必ず書面で残しておきましょう。
書面を交わすことで、双方の認識を明確にでき、安心して手続きを進められます。
墓じまい・改葬と同時進行する場合の注意点
離壇は墓じまいや改葬と同時に進められることが多いため、手続きの順序や必要書類を整理しておくことが重要です。
・改葬許可証の取得
・離壇証明書、埋葬証明書の発行
・墓石撤去や遺骨の取り出し
これらを並行して進める場合、どの段階で寺院に依頼するのかを明確にしておくとスムーズです。特に「離壇料の支払い」と「離壇証明書の受領」のタイミングは事前に確認しておきましょう。
墓じまいの詳しい流れは下記の記事をご覧ください。
↓墓じまいにかかる費用についてくわしく知りたい方はこちら↓
第三者(石材店・行政・霊園管理者)への相談活用
離壇やお墓じまいの手続きは複雑で、寺院との交渉に不安を感じる方も少なくありません。その場合は、石材店や行政窓口、霊園管理者といった第三者に相談するのも有効です。
石材店は墓石撤去や改葬の実務に詳しく、行政は改葬許可証の発行手続きに関する正確な情報を提供してくれます。中立的な立場の第三者を活用することで、寺院とのやり取りも円滑になりやすくなります。
お寺の本音
実際、離壇を切り出される側のお寺はどう思っているのでしょうか。真言宗豊山派の僧侶で、大福寺 副住職を務める山﨑亮秀さんに聞きました。
「少子高齢化などの状況を踏まえると、残念ではありますが、致し方ない流れかと思います。今あるお墓が無縁墓になることは、お寺としてもご先祖様にとっても心苦しいことです。なので、ご相談をいただければ誠意をもって対応いたします」
離壇の流れ(手順)
離壇は、単に「檀家をやめる」と伝えるだけではなく、家族間の合意形成から寺院とのやり取り、そしてお墓じまいや改葬の準備まで、いくつかの段階を踏んで進める必要があります。ここでは、一般的な流れを6つのステップに分けて解説します。
1.家族・親族間での合意形成
まず大切なのは、家族や親族の間で離壇についてしっかり話し合い、合意を得ることです。離壇は先祖代々のお墓や供養の形を変える大きな決断となるため、後から「聞いていない」「反対だった」といったトラブルを避けるためにも、全員で方向性を共有しておくことが重要です。
2.寺院への事前相談(口頭・書面)
家族で合意ができたら、次は寺院に相談します。いきなり通知するのではなく、まずは住職に直接会い、事情を丁寧に説明することが円満な離壇につながります。
また、口頭だけでなく、必要に応じて書面で意思を伝えておくと、後々の誤解やトラブルを防ぐことができます。
3.離壇料(お礼)の確認
寺院によっては離壇料が必要となる場合があります。
法的な義務ではありませんが、長年の供養や管理に対する感謝の気持ちとして渡すのが一般的です。金額や渡し方については、事前に住職に確認し、無理のない範囲で準備しておきましょう。
4.墓じまい・改葬の準備(必要に応じて)
寺院墓地にお墓がある場合は、離壇と同時に墓じまいや改葬の準備が必要です。具体的には、改葬許可証の取得、石材店への墓石撤去依頼、遺骨の取り出しなどが含まれます。これらの手続きは並行して進めることが多いため、スケジュールを整理しておくとスムーズです。
5.離壇証明書の受領
離壇が正式に認められると、寺院から「離壇証明書」が発行される場合があります。墓じまいの場合は、先祖の遺骨が埋葬されていた「埋葬証明書」も渡されます。「埋葬証明書」は、今後の改葬手続きや新しい納骨先で必要になる大切な書類です。必ず受け取り、紛失しないように保管しておきましょう。
6.新しい納骨先・供養先の決定
最後に、遺骨を納める新しい場所を決めます。永代供養墓や納骨堂、樹木葬、合同供養など、選択肢はさまざまです。家族の希望や将来の管理のしやすさを考慮し、無理のない供養方法を選ぶことが大切です。
離壇後の選択肢

離壇を終えた後は、遺骨をどこに安置し、どのように供養を続けていくかを決める必要があります。従来の寺院墓地に代わり、近年は多様な供養方法が選べるようになっています。ここでは代表的な3つの選択肢を紹介します。
民間霊園・公営墓地への改葬
寺院墓地から離壇した後、民間霊園や公営墓地に改葬するケースは多く見られます。
民間霊園は、宗派を問わず利用できるところが多く、立地や設備の選択肢が豊富です。管理体制が整っているため、利便性を重視する方に向いています。
公営墓地は自治体が運営しており、費用が比較的安く、永続性が高い点が魅力です。ただし募集枠が限られており、抽選になることもあります。
改葬によって、アクセスの良い場所や将来の管理がしやすい環境を選べるのが大きなメリットです。
合祀墓
合祀墓とは、複数の遺骨を一つの墓所にまとめて埋葬する形式です。費用が最も安価で、管理の必要もありません。
ただし、一度合祀すると遺骨を取り出すことはできないため、家族や親族の理解を得たうえで選択することが重要です。
「後継者がいない」「費用を最小限に抑えたい」という場合には、現実的な選択肢となります。
永代供養墓・納骨堂・樹木葬
近年人気が高まっているのが、永代供養墓や納骨堂、樹木葬といった新しい供養スタイルです。
・永代供養墓:寺院や霊園が永続的に供養を行ってくれるため、後継者がいなくても安心。
・納骨堂:屋内施設に遺骨を安置する形式で、アクセスが良く、天候に左右されない点が特徴。
・樹木葬:墓石の代わりに樹木をシンボルとする自然志向の供養方法で、費用も比較的抑えられる。
これらは「管理の手間を減らしたい」「宗派に縛られず自由に供養したい」と考える方に適しています。
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、全国に宗派不問の永代供養墓を提供しています。
まとめ

離壇は「檀家をやめる」だけでなく、先祖の供養や家族の将来に関わる大きな決断となります。
メリット・デメリットを理解し、関係者と十分に話し合うことが重要です。トラブル回避には「感謝の姿勢」と「事前準備」がポイントです。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です