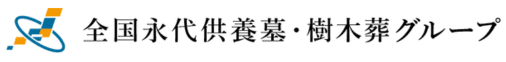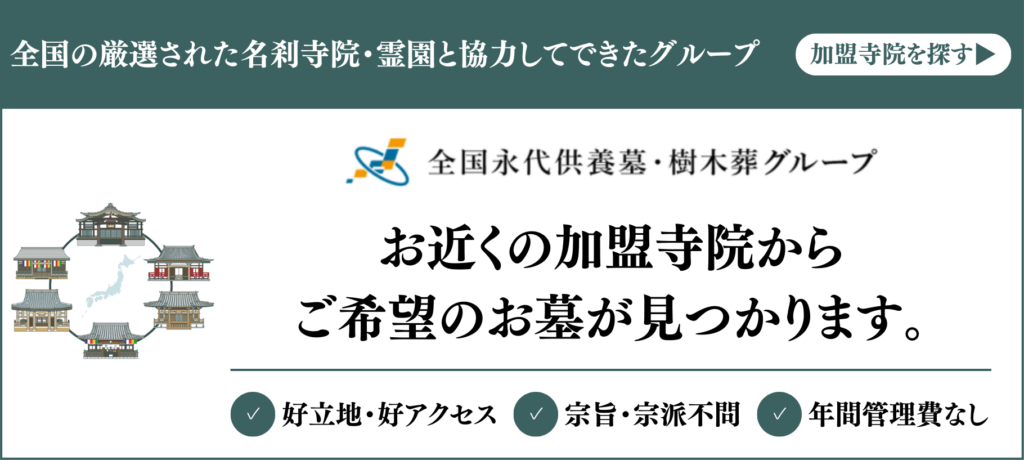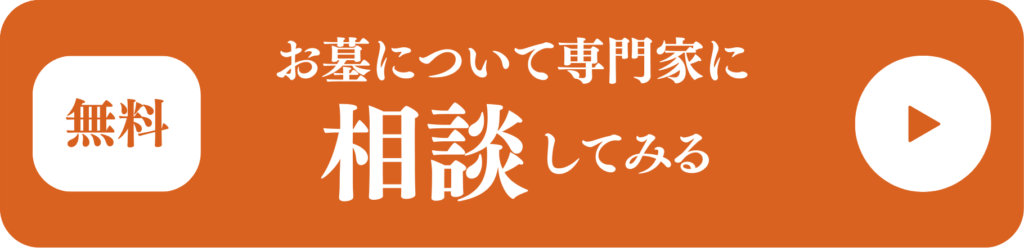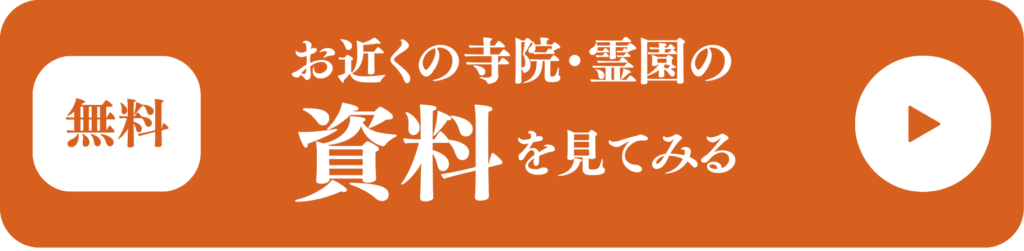ペットの樹木葬とは?種類・費用・手続きから注意点まで完全ガイド

家族の一員として愛されたペットの供養方法として、樹木葬が注目を集めています。
ペット専用から飼い主との合葬、自宅での樹木葬まで選択肢は多様です。この記事では、それぞれの特徴や費用相場、実際の手続きから注意点まで、愛するペットにとって最適な供養方法を見つけられるよう、総合的に解説します。

樹木葬とは?基本的な仕組みと従来のお墓との違い

「樹木葬」とは、墓石の代わりに樹木や草花に囲まれた自然環境へ遺骨を埋葬・納骨するお墓のことで、シンボルツリーを用いたり、花や芝生が植えられた庭園に埋葬される形式が一般的です。
多くの樹木葬では「永代供養」として、霊園や寺院が遺骨の管理や供養を永代にわたっておこなうため、後継ぎが不要で維持管理の負担が軽減されるという大きなメリットがあります。さらに、従来の墓石を建てるお墓と比較して費用を安く抑えられる傾向にあり、また宗旨宗派を問わず利用できることから広く支持されており、自然の中で永眠したいという方々にも選ばれています。
最新の調査結果では、新たにお墓を購入する方の約半数(48.7%)が樹木葬を選んでおり、その人気の高さがうかがえます。
出典:【第15回】お墓の消費者全国実態調査(2024年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向(いいお墓)
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、そのような樹木葬を多数ご案内しております。
ペット樹木葬の3つの種類と選び方

ペットの樹木葬は、主に「ペット限定タイプ」、「ペットと飼い主の合葬タイプ」そして「自宅敷地内での埋葬」の3パターンに分けられます。
また、霊園における埋葬形式には更に「合祀・合葬型」「集合埋葬型」「個別埋蔵型」の3つの選択肢があります。
ペット専用の樹木葬(ペット霊園)
ペット限定の樹木葬は、樹木葬サービスを提供する民営のペット霊園での埋葬を指します。ペット霊園では、葬儀、火葬、納骨をパッケージ化したプランを提供していることもあるため、契約詳細を事前に把握することが大切です。
長所としては、専門的な維持管理が期待できる点が挙げられます。ただし、ペット霊園は一般的な霊園と比較して行政チェックが緩い傾向にあるため、急な倒産や閉園というリスクを考慮する必要があります。そのため、契約前には必ず評判を調査し、現地視察をおこない、信頼できる霊園かどうかを自身で判断することが望ましいでしょう。
ペットと飼い主が一緒に入れる樹木葬
このタイプの樹木葬では、ペットと飼い主が同一の区画に埋葬されることが可能です。これは、「愛するペットと同じ墓に眠りたい」「ペットとともに自然に還りたい」という飼い主の思いを叶える点が大きな魅力といえるでしょう。
ただし、多くの樹木葬では決められた期間を経過すると遺骨を個別区画から移し、他の遺骨と一緒に合祀することも多いです。合祀の際に、ペットと人間の遺骨が別々に扱われるケースもあるため、契約前に必ず詳細を確認することが必要です。また、この形式の樹木葬は比較的新しいサービスのため、対応している墓地や霊園の数が限られているという課題もあります。
全国永代供養墓・樹木葬グループの加盟寺院のなかには、ペットと眠ることができる樹木葬もございます。ぜひ、お近くの樹木葬をご確認ください。
自宅の敷地での樹木葬
自宅の庭などの所有地にペットを埋葬することは、法的に問題ありません。
これは、人間の遺体や遺骨の処理に関して規定された法律(墓埋法)がペットには適用されないためです。ただし、公共用地や他人の所有地に無断で埋葬することは、不法投棄として法的問題を引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。
自宅での樹木葬は、愛するペットの存在を身近に感じることができ、ペットロスを克服する助けになるという心理的なメリットがあります。また、実用的な面では、ペット霊園への移動が不要で、こまめな墓所の手入れが可能という点が挙げられます。費用については、すべてを自分でおこなえば支出はありませんが、悪臭や害虫・獣害のリスクを回避するために火葬業者での火葬と遺骨の粉砕依頼を強く推奨します。
埋葬時には、シンボルとなる樹木を育てます。樹木の栽培が困難な場合は、比較的育成しやすい草花などを植栽することも可能です。庭がない住環境では、ベランダでも使用できるペット向け樹木葬キットを検討することもできます。
埋葬方法の3タイプ|合祀・合葬型、集合埋葬型、個別埋葬型の特徴と選び方
霊園を活用したペット樹木葬には、主に3つの埋葬形式があります。
合祀・合葬型

個別区画を設けずに共有区画に埋葬する形式です。同一の穴に遺骨を埋葬することになるため、遺骨が混ざり合います。費用が安価で、維持管理費もかからないという利点がありますが、愛するペットが他の骨と混ざってしまうことに抵抗感を覚える方もいます。
集合埋葬型

合祀・合葬型と同じように他の方とシンボルや墓標を共有し、共同スペースに遺骨を埋葬する形式です。ただし、骨壷や骨袋のまま埋葬される点は合祀・合葬型とは異なります。遺骨は土に還されることも多いですが、骨壷で一定期間埋葬され、その後は合祀されるという場合もあります。
個別型

個別区画ごと1つのシンボルや墓標があり、完全個室に遺骨を埋葬する形式です。他の方と遺骨が混ざってしまうという心配はありません。また、集合型と同様に骨壷で一定期間埋葬され、その後は合祀されるという場合もあります。全国永代供養墓・樹木葬グループの樹木葬では、期限を設けず永代にわたって完全個別で眠ることのできる樹木葬をご紹介しています。
| 埋葬方法 | 特徴 |
| 合祀・合葬型 | 共有区画に埋葬。費用は安価だが遺骨が混じることに抵抗がある方もいる。 |
| 集合埋葬型 | 骨壷で一定期間埋葬され最終的に合祀される。 |
| 個別型 | 個別区画に完全個室で埋葬。集合型と同様に後から合祀されるケースもある。 |
ペット樹木葬にかかる費用相場

ペット樹木葬の費用は、地域や選択する埋葬形式によって大幅に変動します。
ペット専用樹木葬の費用相場
民営のペット霊園を利用する場合、初期費用は5千~10万円が相場です。維持管理費はかからない場所も多いですが、なかには維持管理費を求められる場合もあるため、無料~5千円程度が目安となります。
ペットと一緒に入れる樹木葬の費用
人とペットが合葬できる樹木葬の場合、初期費用は5~100万円が相場です。ペット専用樹木葬と比較すると割高ですが、これはあくまでも前述した墓地埋葬法が適応される人間のお墓であるためです。維持管理費はかからない場所も多いですが、なかには維持管理費を求められる場合もあるため、無料~1万円程度が目安となります。
自宅での樹木葬の費用
自宅の敷地を活用して樹木葬をおこなう場合、すべてを自分で実施すれば費用は発生しません。しかし、衛生的観点から、火葬してから埋葬することが推奨されているため、民営のペット霊園や火葬業者に火葬を依頼するのが適切でしょう。費用はペットの体重などによっても変動しますが、1~10万円ほどが相場です。火葬後は、市販のペット樹木葬キットを活用して埋葬する方法もあり、この場合の費用は1~5万円程度です。
樹木葬費用の内訳|基本料金と追加費用
ペットと一緒の樹木葬を利用する場合、初期費用以外にもさまざまな費用が発生します。費用相場や内訳は以下の通りです。
1.永代供養料(墓地・霊園使用料含む)
樹木葬はお墓を継いでいく必要のない「永代供養」であることが一般的です。永代供養料とは、お寺や霊園にお墓を永代にわたって管理・供養してもらうための全てが含まれた費用です。相場は先ほど解説した種類や条件によって変わりますが、合祀・合葬型は5~30万円、集合埋葬型は20~50万円、個別埋葬型は40~100万円ほどです。
2.納骨法要料
納骨法要料とは、ご遺骨を埋葬する際に、僧侶にお経を読んでいただくお布施のことです。お布施のため、お気持ちで包むことが基本ですが、相場は3~5万円です。
3.墓誌・彫刻料
墓地・霊園によっては、墓標(お墓や故人の目印)として墓誌やプレートに名前を彫刻できるところもあります。彫刻料の相場は3~5万円です。
4.維持管理費
昔ながらのお墓では基本的に1~2万円程度かかると言われている年間管理費ですが、永代供養である樹木葬はこのような維持費がかからないことが一般的です。ただし、樹木葬では草木の管理がどうしても必要になることから、なかには年間管理費がかかる墓地・霊園もあるため事前に確認しましょう。
| 費用の内訳 | 費用の目安 |
| 永代供養料(合祀・合葬型) | 5~30万円 |
| 永代供養料(集合埋葬型) | 20~50万円 |
| 永代供養料(個別埋葬型) | 40~100万円 |
| 納骨法要料 | 3~5万円 |
| 墓誌・彫刻料 | 3~5万円 |
| 維持管理費 | 1~2万円(無料の場合もある) |
樹木葬の費用についてより詳しく知りたい方はこちら

自宅でペットの樹木葬をおこなう方法

ここでは、自宅でペットの樹木葬をおこなう場合の手順や注意点を紹介します。
自宅埋葬の法律・条例|違法にならないための確認ポイント
自宅の敷地内であれば、法的にはペットの樹木葬をおこなうことに問題はありません。
ただし、ペットの遺体は法的に「廃棄物」とみなされることもあり、他人の所有地や公園などの公共用地に埋葬すると、不法投棄として法的問題を引き起こす恐れがあります。
自分の土地であっても、近隣からネガティブに受け取られてトラブルになる可能性も考慮し、周囲に十分配慮した上で進めるましょう。特に、隣接地との境界が不明確な場所は避けるべきでしょう。
自宅での樹木葬の手順
自宅の庭にペットを埋葬する場合、以下の手順と注意点を参考にしましょう。
穴を深く掘る
土葬の場合、他の動物に掘り返されたり、悪臭の原因になったりするのを防ぐため、遺体や遺骨の5~10倍程度、または1~2m程度の深さを目安に掘ります。
火葬または粉骨した遺骨を埋葬する場合は、30cm程度の深さが目安です。雨風から保護するため、囲いや覆いなどで対策することも推奨されます。
腐食しやすい布を敷く
遺体を埋葬する場合、腐食・分解を促進するために、穴の底に綿などの天然素材の布を敷きます。段ボールや消臭効果のある石灰を敷くことも可能です。土に還りにくいペットの首輪などの副葬品は控えましょう。
埋めた場所に土を盛る
埋葬した地面は、将来的に土中に空洞ができて沈下する可能性があるため、30cm程度高く土を盛るようにします。後で土をかぶせられるように、埋葬場所を選定することも大切です。
樹木を植栽する
すでに庭にある樹木の近くに埋葬するか、埋葬した上に新たにシンボルツリーを植栽します。種を蒔く場合は、遺体が樹木の根の発育を妨げる可能性があるため、遺体の真上には蒔かないように、少し位置をずらして蒔くことが推奨されます。特に遺体を埋葬する場合、土に還るまでに数年~数十年を要することもあります。
樹木葬キットの活用方法
自宅に庭がない場合や、土を掘ったり埋めたりする手間を省きたい場合は、市販のペット向け樹木葬キットを利用する方法もあります。これらのキットは、火葬後の遺骨や遺灰を収める容器とシンボルツリーがセットになっているのが一般的で、室内に飾るタイプやプランター、庭に埋めるタイプがあります。
粉骨の必要性と方法
自宅での樹木葬において、遺体をそのまま埋葬すると悪臭や害虫・獣害トラブルのリスクが高まります。これらのリスクを回避するためにも、火葬・粉骨してから埋葬することが推奨されます。粉骨は、遺骨を土に還りやすくするためにも有効です。
ペット火葬業者などに粉骨を依頼する
専門業者であれば、専用の粉砕機を使って遺骨をパウダー状に加工してくれます。費用は、犬や猫などのペットであれば1万円程度が目安です。
自宅で粉骨する
ペットの遺骨は高温で火葬されているため脆くなっており、ハンマーなどで砕いて粉骨することも可能です。しかし、大切なペットの遺骨を手作業で粉骨することに抵抗がある場合は、無理をせずに業者に依頼することをおすすめします。
ペットの樹木葬を選ぶ際の注意点

ペットの樹木葬で満足のいく供養をおこなうためには、いくつかの注意点や確認事項があります。
宗教・宗派の確認
霊園や寺院が提供する樹木葬を利用する場合、宗教・宗派の制限がないかを確認することが重要です。民営の霊園はほとんどが宗教不問ですが、寺院に併設されたペット霊園や、人と一緒に埋葬する樹木葬の場合、その寺院の檀家になる必要があるケースもあります。檀家になると、定期的に会費やお布施を支払う必要が生じるため、宗教不問の樹木葬であるかを事前に確認しておきましょう。
将来の管理体制について
霊園での樹木葬の場合、管理者がお墓の世話や供養を継続してくれるため、遺族は希望する時にお参りに行くだけでよく、清掃や草取りは不要です。しかし、自宅での樹木葬の場合、お墓を管理するのは自分たちだけです。将来的に転居したり、供養する人がいなくなったりする可能性も考慮する必要があります。一度埋葬すると遺骨を後から取り出すことがほとんど不可能な点にも注意が必要です。
家族・近隣への配慮事項
樹木葬は比較的新しい埋葬方法であり、家族や親戚から理解を得られない可能性もあります。特に、一般墓を希望する家族がいる場合や、埋葬後に遺骨を移動できない場合があるため、事前に家族としっかり話し合い、共通認識を持つことが大切です。
自宅で樹木葬をおこなう場合、近隣住民がネガティブに受け取る可能性も考慮しましょう。また、煙や匂いが周辺に漏れるため、線香の使用も控えた方がよい場合もあります。
自宅樹木葬の環境対策|異臭・害虫・近隣トラブルの防止方法
自宅での樹木葬は、環境面での配慮が必要です。
埋葬場所の選定
日当たりや風通しがよく、水たまりができない水はけのよい場所を選びましょう。土が適度な湿度を含んでいること、人に踏まれない場所、そして人目につきにくい場所が埋葬に適しています。
悪臭や虫害トラブル
遺体をそのまま埋葬すると、悪臭や害虫・獣害トラブルのリスクが高まります。これらのリスクを回避するため、火葬・粉骨してから埋葬することが推奨されます。
樹木の選択
せっかく植栽した樹木が枯れてしまうと悲しい思いをする可能性があるため、栽培に慣れていない場合は、育てやすい樹木や花を選ぶか、もともとある樹木の傍へ埋葬するのがおすすめです。
将来的な土地の売却・転居
自宅の転居や土地の売却をおこなう場合、庭にペットのお墓があることを説明する必要があり、買い手からネガティブに受け取られ、トラブルの原因となる可能性があります。転居や売却の可能性がある場合は、自宅での樹木葬は避ける方が無難です。ペットの遺体や遺骨は土に還るまでに数十年以上を要することもあります。
樹木葬でよくあるトラブルについてより詳しく知りたい方はこちら
ペット樹木葬の手続きと流れ

ペットの樹木葬の手続きは、一般的な人間の樹木葬と同様に、事前にしっかりと確認し、準備を進めることが重要です。
樹木葬選びのポイント
樹木葬を選ぶ際は、以下の点に注目しましょう。
ペット合葬対応
まず、希望する霊園がペットとの合葬に対応しているかを確認しましょう。
宗教・宗派の制限
宗教・宗派を問わず利用できるかを確認し、特に寺院墓地の場合は檀家になる必要があるかを確認しましょう。
埋葬方式
合祀・合葬型、集合埋葬型、個別埋葬型のどの埋葬方式に対応しているか、また、個別型であっても一定期間後に合祀されるのかなど、将来的なことも含めて確認しましょう。
費用
初期費用だけでなく、永代供養料、納骨法要料、墓誌・彫刻料、維持管理費など、全ての費用詳細を事前に確認することが大切です。特に納骨料は遺骨の数だけ発生する場合があるので、複数のペットの納骨を考えている場合は全体での費用を確認しましょう。
霊園や寺院の信頼性
評判を調査し、実際に現地を見学し、霊園や寺院の雰囲気や管理体制を自分の目で確かめ、信頼できる場所を選ぶことが推奨されます。
アクセス
お参りしやすい立地にあるかどうかも重要なポイントです。
申し込みから納骨までの流れ
具体的な手続きや流れは霊園によって異なりますが、一般的には以下のステップが含まれると考えられます。
1.霊園の選定と事前確認
上記のポイントを踏まえ、希望に合った霊園を選び、詳細な情報を確認します。
2.契約
霊園を選んだ後、契約を締結します。この際に、永代使用料や銘板彫刻代など、初期費用を支払うことが一般的です。
3.納骨の準備
ペットの火葬や粉骨をおこない、納骨の準備を進めます。
4.納骨日の決定
霊園と相談し、納骨の日程を決定します。
納骨当日の流れ
納骨当日は、決定した日時に霊園を訪れ、遺骨を埋葬してもらいます。納骨料は、納骨時に支払うことが一般的です。霊園によっては、埋葬の立ち会いも可能です。その後も、定期的に僧侶による合同供養会を実施している霊園もあります。
樹木葬の手続きなどに関するご相談はこちら
ペット樹木葬のメリット・デメリット

ペット樹木葬にはメリット・デメリットの両方があります。それぞれについてよく知ってから、ご自身のご希望に合う供養の方法を選びましょう。
樹木葬のメリット
ペットとの合葬可能な樹木葬を選ぶことには、飼い主にとって多くのメリットがあります。
ペットとの合葬の願いを実現
「ペットと同じ墓に眠る」という希望を叶えられます。
自然回帰
最後には大自然に還ることができます。
費用を軽減
従来型の一般墓と比較して、購入・管理コストを軽減できる傾向があります。
明るく自然豊かな雰囲気
樹木葬のある霊園は、緑豊かで花木に囲まれた明るい雰囲気の中で供養できることが多いです。
管理の手間が軽減
霊園に埋葬した場合、お墓の管理や供養は霊園の管理者がおこなってくれるため、遺族にとって清掃や草取りなどの手間が省けます。
ペットロスからの回復
自宅での樹木葬の場合、ペットの存在を身近に感じられ、シンボルツリーの成長とともに心の傷が癒されるなど、ペットロスを克服する支えになる可能性があります。
樹木葬のデメリット
一方で、ペットの樹木葬には考慮すべきデメリットも存在します。
選択肢が限られる
ペットと人が一緒に埋葬できる樹木葬を取り扱っている墓地や霊園は、まだ数が少ないのが現状です。特に地方では、自宅から行ける範囲で見つけるのが困難な場合があります。
遺骨の取り出しが困難
多くの樹木葬では、一度埋葬すると後から遺骨を取り出すことがほとんど不可能です。これは、転居などで別の場所にお墓を移したい場合に問題となる可能性があります。
家族の理解が必要
比較的新しい供養方法であるため、家族や親族から樹木葬への理解が得られない場合があります。改葬ができないケースも多いため、事前に十分な話し合いが必要です。
大人数での使用や承継には不向き
樹木葬の区画は1~4名向けが多いなど、大人数での利用や代々承継していくお墓としては向かない場合があります。
特に自宅でのペットの埋葬には以下のようなリスクがあります。
悪臭・害虫トラブル
遺体を火葬せずにそのまま埋葬すると、悪臭や害虫・獣害(野良犬などに掘り返される)のリスクが高まります。
土地の売却・転居時の問題
将来的に土地を手放したり転居したりする場合、庭にペットの墓があることが買い手からネガティブに受け取られ、売却が困難になる可能性があります。
将来の管理不足
埋葬を自分たちでおこなうため、将来的に供養する人がいなくなる「無縁仏」の状態になる可能性も考慮が必要です。
他の供養方法との比較
樹木葬以外にも、ペットの供養方法にはいくつか選択肢があります。例えば、一般的なお墓や納骨堂への埋葬、散骨、手元供養などが挙げられます。これらの供養方法と比較し、ご自身の生活スタイルや希望に合った方法を選ぶことが重要です。
樹木葬に向いている方・向いていない方
樹木葬が適している方は以下の通りです。
- 「ペットと同じ墓に眠りたい」「自然に戻りたい」という願いがある方
- 墓石のお墓よりも費用を軽減したい方
- 墓地の承継者がいない、または将来的にいなくなることに不安がある方(霊園での永代供養)
- お墓の管理や清掃の手間を省きたい方
- ペットロスを克服するために身近に存在を感じたい方(自宅での樹木葬も含む)
- 自然豊かな明るい雰囲気の場所で供養したい方
樹木葬に向いていない方は以下の通りです。
- 埋葬後に遺骨を取り出す可能性がある方
- 家族や親族が樹木葬に理解を示さない場合
- 大人数での利用や、代々継承していく従来型のお墓を希望する方
- 将来的に自宅を売却する可能性が高い、または転居の予定がある方(自宅での樹木葬の場合)
樹木葬のメリット・デメリットについて、よりくわしく知りたい方はこちら
まとめ

近年、ペットを家族の一員と捉え、その供養にこだわる方が増加しており、樹木葬が注目されています。ペットの樹木葬には、主に「ペットと飼い主の合葬タイプ」「ペット専用のタイプ」、そして「自宅の敷地を活用するタイプ」の3種類があります。それぞれのタイプによって費用相場が異なり、ペット専用霊園では5千~10万円程度、人との合葬可能な霊園では20~100万円程度、自宅では火葬費用を含めて無料~5万円程度が目安となります。
霊園を利用する場合は、永代供養料、納骨法要料、墓誌・彫刻料、維持管理費といった費用内訳を事前に確認することが重要です。自宅で樹木葬をおこなう場合は、法律上は問題ありませんが、悪臭や虫害、近隣トラブルを避けるために火葬・粉骨を強く推奨され、深く穴を掘り、腐食しやすい布で遺体を包むなどの適切な手順を踏む必要があります。庭がない場合は、樹木葬キットの活用も検討しましょう。
樹木葬を選ぶ最大のメリットは、愛するペットと共に自然に還る願いを実現し、継続的な供養を受けられることです。しかし、一度埋葬すると遺骨を取り出せないことが多い、ペット対応の霊園がまだ少ない、家族の理解が必要といったデメリットも存在します。特に自宅での樹木葬は、将来の引っ越しや土地の売却、長期的な管理の問題も考慮し、慎重に検討する必要があります。
選ぶ霊園や埋葬方法によって費用やメリット・デメリットが異なるため、愛するペットに対して納得して供養ができるよう、口コミを調べたり、現地を見学したりするなど、事前にしっかりと確認した上で申し込みましょう。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です