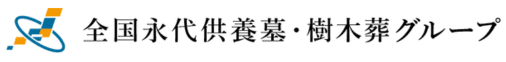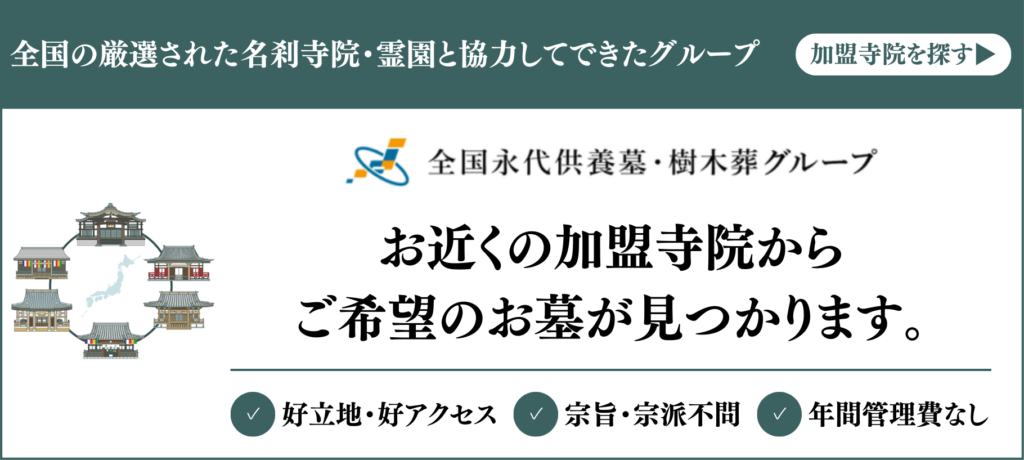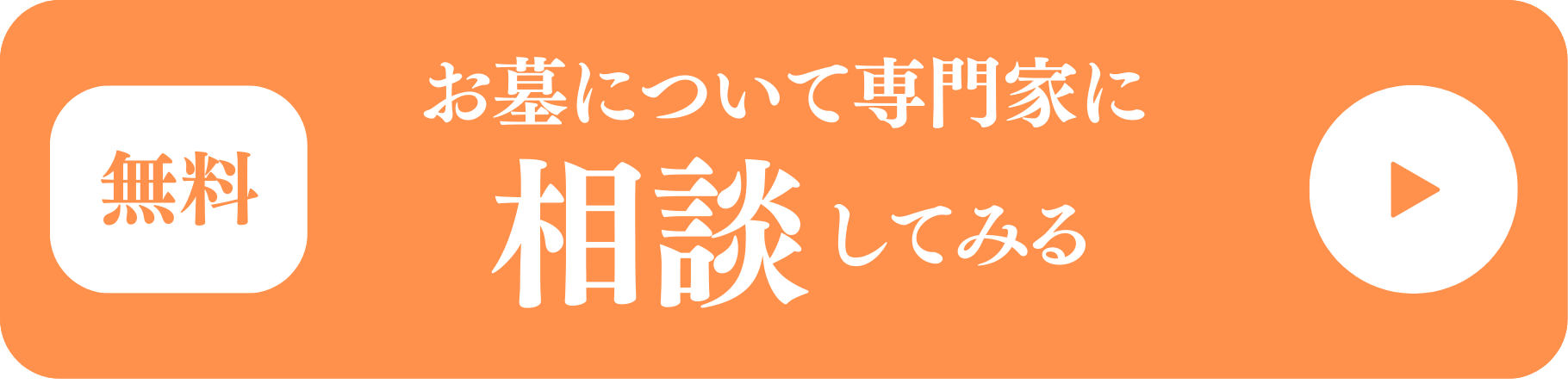散骨とは?永代供養との違い、費用相場やメリット・デメリットを解説

これまでの埋葬方法は、遺骨をお墓に納めることが一般的でしたが、少子高齢化や核家族化を受けて、お墓の維持や継承が困難になってきています。
その流れを受けて、近年埋葬方法が多様化してきており、その中でもお墓のいらない「散骨」という埋葬方法があります。
散骨をこれから検討される方に向けて、この記事では散骨とは何か?永代供養の違いは何か?また、実際にかかる費用相場や埋葬方法、そして散骨のメリットやデメリットまでわかりやすく解説します。

散骨とは?

散骨とは、遺骨を粉末(パウダー)状にして海や山林などに撒き、自然環境へ還す埋葬方法を指します。火葬直後の遺骨だけでなく、近年増加する墓じまいのあとの埋葬方法としても注目されています。また、遺骨のすべてを散骨するだけでなく、一部だけを散骨することも可能です。
永代供養と散骨の違い

永代供養とは?
永代供養は、寺院や霊園などの墓地の管理者に「永代供養料」を支払い、遺族に代わって永代にわたって遺骨を管理・供養してもらうことを意味します。
お墓の継承者がいなくても安心な点や子孫に負担をかけない点など、そのメリットから近年多くの方の注目を集めるようになりました。
「永代供養」と「散骨」 似ているようで違う
永代供養と散骨の最大の違いは「墓標の有無」です。永代供養墓であれば、手を合わせる墓標が存在しますが、散骨をしてしまうと、手を合わせる場所がありません。
「継承者が不要」「遺骨の管理が不要」などの点は永代供養と共通するところですが、厳密には永代供養と散骨は異なります。
散骨の3つの方法とそれぞれの費用相場

散骨にはいくつかの方法があります。それぞれを費用とともに紹介します。
1.海洋散骨
海に遺骨を散骨することを「海洋散骨」と呼びます。海岸から数キロ程度離れた海の上で、水溶性の袋などに包まれた遺骨を海に撒くことが一般的です。海洋散骨には以下の3つの方法があります。
代行散骨
遺族の立会いが不要で、散骨のすべてを業者が代行する海洋散骨の方法です。業者から証明写真や散骨実施証明書が発行・郵送されます。
費用は1体あたり5万円程度です。
合同散骨
複数のご遺族が乗り合わせて散骨をおこなう方法です。
費用は安く抑えられますが、他の方も同乗しているため、気持ちを落ち着けてお別れができないこともあります。また、乗り合いとなるため、1家族で同行可能な人数も2~3名程度に制限されることが多いです。
費用相場は10~15万円程度となっています。
個別散骨
海洋散骨の際にご遺族のみが立ち会うパターンです。亡くなった故人やご先祖様を落ち着いてお見送りできるのが特徴です。
家族だけで船を貸切るため費用相場は高く、20~40万円程度か、それ以上かかるのが一般的です。
山林散骨
山や森林の中で散骨する方法です。
散骨業者の管理する山林、もしくは所有権を持っている自分の山などに遺骨を持参し、土の中へ埋葬せず、樹木の根元などへ遺骨を撒きます。費用相場は5~20万円程度となっています。
宇宙葬・空中葬
遺骨を気球で成層圏まで飛ばして散骨をするバルーン葬や、ロケットで遺骨や位牌を入れたカプセルを飛ばす散骨方法です。ロケットでの散骨は、遺骨を打ち上げたのちに大気圏突入時に燃え尽きるプランや、宇宙を飛び続けるプランなどもあります。
費用相場はバルーン葬で30万円程度、ロケットでの散骨は80~100万円ですが、人工衛星軌道を周回したり、宇宙空間を飛び続けるプランではより高額になります。

散骨をおこなう3つのメリット

散骨をおこなうメリットは3つあります。
費用を抑えることができる
墓地や霊園でお墓を建てる場合、おおよそ200万円ほどかかります。この費用と比べると、圧倒的に安くなります。
お墓の管理が必要なくなる
散骨すると、管理や供養の必要がなくなるため、子供たちの負担を減らすことができます。
また、お墓の継承者のことを考えなくてよいのもメリットです。
故人の遺志を尊重できる
自然に還りたい、自分のゆかりのある場所に還りたいなど、故人の遺志を汲み取った埋葬方法を選べます。
散骨をおこなう3つのデメリット

一方、散骨をおこなうデメリットもあります。
墓標がない
散骨をしてしまうと、心のよりどころとなる「お墓」がなくなってしまいます。
人の立ち入りが難しい山林散骨であると、命日やお盆、お彼岸などの故人を偲ぶタイミングで手を合わせる場所がなく、残された家族が寂しさを感じてしまうことも多いようです。
周囲の理解を得るのが難しい
散骨は比較的新しい埋葬方法のため、本人が希望しても家族や親族など、周囲からの理解を得ることが難しい場合が多いです。残された家族が嫌がる可能性があります。
散骨後の遺骨は取り戻せない
一度散骨してしまうと、手元へ取り戻せないのも散骨のデメリットです。別のお墓への納骨もできなくなってしまうので、散骨する場合は慎重に検討する必要があります。
散骨における注意点
ここでは散骨についての注意点を紹介します。
散骨の前に粉骨をする必要がある
遺骨をそのまま撒くことはできません。遺骨とわからない大きさまでパウダー状にこまかくする必要があります。
目安は2mm以下で、守らずに散骨すると遺体遺棄罪(刑法190条、懲役3年以下)に問われる可能性もあるので注意しましょう。
散骨をおこなっても問題のない場所か確認する
散骨は違法ではありませんが、自治体によって散骨を禁止、もしくは避けるべき場所が条例で定められている場合があるので確認しましょう。
水源地周辺や漁場、養殖場、観光地や観光ルート、そして他人の所有地はトラブルの原因となります。
また、条例などの決まりが無くても他人に迷惑が掛からないように常識の範囲内でおこないましょう。
自然環境へ配慮する
お供え物やお花などについても、自然に還るものを選びましょう。ビニールや金属物などの人工物も避けましょう。
喪服ではなく平服を着る
一般市民への配慮として、散骨当日は人目につきやすい喪服は避けるのが無難です。
改葬許可が必要かどうか確認する
既にあるお墓からご遺骨を取り出して散骨をする場合には、墓じまいや改葬といった手続きによって散骨が可能になります。
自治体によっては「改葬許可」が必要なところもあったり、散骨では改葬許可が出ない自治体もあるので、事前に確認しましょう。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
散骨以外の供養方法

散骨以外の供養方法では、永代供養墓を選ばれる方が多いです。永代供養墓は下記の種類があります。
①合祀・合葬墓(石材型)

合祀・合葬墓は石材型の永代供養墓のなかの一種で、共有スペースにほかの方の遺骨と一緒に埋葬されるお墓です。ほかの方と一緒に埋葬されることで、スペースが少なくてすむため、費用相場は最も安く5~30万円です。
費用を大幅に抑えられることが最大のメリットですが、合祀については慎重に検討するとよいでしょう。ほかの方の遺骨と一緒に埋葬されることや、お参りにきた際に手をあわせる場所がないことに抵抗がある方も少なくありません。
②集合墓(石材型)

集合墓は石材型の永代供養墓のなかで、埋葬方法が集合安置のお墓です。合祀・合葬墓と同様に共有スペースにほかの方と一緒に埋葬されますが、骨壷のまま安置するため、モニュメントや像は合祀・合葬墓よりも比較的大きくなります。費用相場は合祀・合葬墓よりは上がり、20~50万円ほどです。
骨壷のまま安置されるものの、ほかの方と共同スペースに埋葬されることや、手をあわせる場所がないことに抵抗がある方も少なくありません。合祀・合葬墓と同様に家族や親族と慎重に相談するとよいでしょう。
③個別安置墓(石材型)

個別安置墓は石材型の永代供養墓で、個人や家族で個別に眠ることができます。マンションのような個別のスペースがあるため費用相場は50~200万円です。
屋外にあり、石でできている点や、完全個室に家族だけで眠れる点など、ほかの永代供養墓にはない今までのお墓のよい特徴が保たれていることが大きなメリットです。個別安置が可能ですが、永代供養墓であるため、年間管理費などの維持費もかからず、永代にわたってお寺や霊園に管理してもらえる点も安心です。昔ながらの一般墓よりは大幅に費用が抑えられるものの、ほかの永代供養墓と比べると安くはありません。
④樹木葬

墓石の代わりに樹木を用いたり、埋葬場所が草花に囲まれているような永代供養墓です。自然志向な点や永代供養であることから、近年注目を集めています。埋葬人数や埋葬方法によっても変わりますが費用相場は5~100万円です。
昔ながらの石でできたお墓に対して緑に囲まれた明るい雰囲気を持っており、自然に包まれ、最後は自然に還りたい方に選ばれています。先ほど解説した、合祀・合葬、集合安置、個別安置と、それぞれ埋葬方法はお墓や各墓地によっても違うため、その点も踏まえてよく検討するとよいでしょう。
⑤納骨堂

納骨堂は遺骨を専用のスペースに納骨できる屋内施設です。永代供養がついている施設も多く、ロッカー式や仏壇型、自動搬送式など様々な種類があるため費用相場は20~150万円です。
屋内にあるため、天候に左右されず冷暖房や照明、バリアフリー設計など設備が整っている施設が多いですが、昔ながらのお墓の雰囲気と大きく変わるため、風情を感じられないという方もいます。また、屋内施設の運営には管理コストが必要なため、永代供養がついていても年間管理費がかかるところもある点は注意しましょう。
⑥永代供養付き一般墓(個人墓型)

昔ながらの一般墓と全く同じもので永代供養がついているお墓もあります。大きな墓石を用い、形状は一般墓と変わらないため、費用相場は永代供養墓の中で最も高く100~150万円です。
13年、33年など一定期間を過ぎると合祀になる場合がほとんどで、合祀されるまでの期間は年間管理費がかかるところもありますので注意しましょう。
散骨と永代供養墓の比較
| 永代供養墓 | 散骨 | |
| 埋葬方法 | 所定の墓地に遺骨を埋葬・納骨 | 遺骨を粉骨して土をかけずに撒く |
| 費用 | 5~150万円 | 5~30万円程度(海洋・山林の場合) |
| 墓標の有無 | 〇 | × |
| 遺骨の管理・手続き | 納骨時に「埋葬許可書」墓じまい「改葬許可書」 | 役所への相談 |
| 法律に則った埋葬 | 〇 | △(明確な法律はなし) |
| 墓地としての経営許可 | 〇 | × |
永代供養墓と散骨の違いを表にまとめました。
永代供養墓は正式な墓地として、都道府県知事から経営許可を取得されて運営されており、墓地を経営できるのは、公共団体・公共法人・宗教法人に限られます。
霊園や寺院では公的に遺骨を守る役割を担っているため、今後の安心感も大きいものになります。
永代供養墓によくある質問

散骨をおこなう際によくある質問とその回答についてご紹介いたします。
散骨がよくない理由は?
散骨に対して、抵抗を感じられる方もいらっしゃいます。
その理由として、宗教上の問題や法的な問題を指摘される方や、手を合わせる場所がないことに対する抵抗感が挙げられます。墓標がないため、遺族が故人を偲ぶ時に寂しさを感じてしまうことも多いようです。
散骨には多くの注意点があるので、それらを確認しながら慎重にすすめる必要があります。
お墓に入らない方法はありますか?
散骨はもちろん、樹木葬も、遺骨を納骨せずに供養できる場合があります。
樹木葬は木々や花々をシンボルとして、それら樹木の下で眠り、自然に還ることのできる供養方法として知られています。
火葬後に遺骨を自宅などに置いておく「手元供養」もありますが、実際に管理することになる遺族のほとんどは永代供養墓などへ納骨することが多いです。
日本では散骨は禁止されていますか?
日本には散骨に関する規制や法律は存在しないため、節度をもったお別れの儀式であれば違法にはなりません。
しかし、遺骨をそのまま散骨すると違法となる場合もあるので、散骨を検討する際は必ず注意点をご確認ください。
まとめ

以上、散骨と永代供養について解説しました。
散骨は一度してしまうと墓標がない、というのが最大のポイントです。
散骨という選択肢は、本人は気にしないことが多いですが、残された家族が抵抗感を覚えることも多いようです。
埋葬方法で迷ったとき、永代供養について詳しく知りたくなった方は、ぜひ全国永代供養墓・樹木葬グループにご相談ください。専門スタッフが対応させていただきます。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です