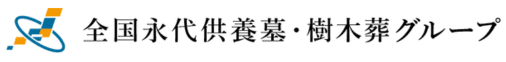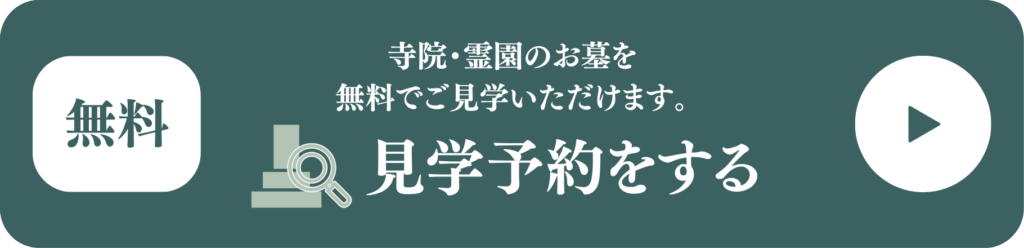永代供養をいつするか決める3つの方法!早めるメリットと手順を解説
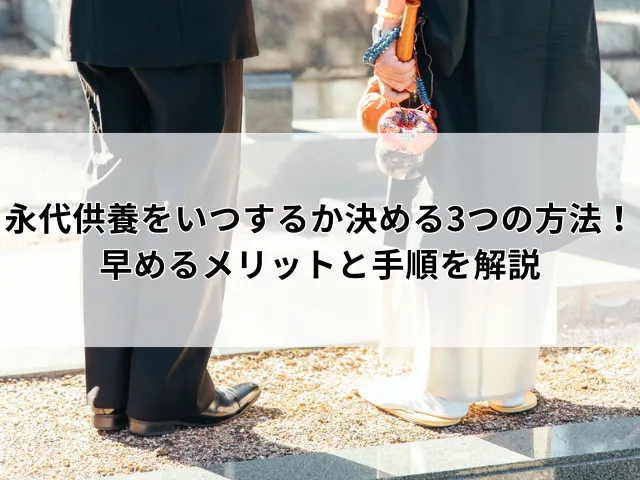
永代供養をいつするかを決めるには3つの方法があり、早いほどメリットが得られるのをご存知でしょうか。
この記事では、一般的に永代供養がおこなわれる時期やおすすめのタイミングについて解説しています。
速やかに永代供養にする手順や、永代供養の期間における注意点までご紹介していますので、いつするか迷っている方はぜひご覧になりお役立てください。

永代供養はいつする?

永代供養はいつするのか、そもそも知識がない方でも理解が深められるよう、分かりやすく解説します。
永代供養とは?
永代供養とは、亡くなった方の遺族や子孫に代わって、霊園や寺院が遺骨の管理や供養をおこなうことをいいます。
昔ながらの墓地へ墓石を建てるお墓とは違い、継承者がいなくても申し込みができ、子どもへ墓守りの負担をかけたくないご家庭にも最適です。
最新の調査結果によると、跡継ぎがいらないお墓を選ぶ方は新規購入者のうち65%を占めており、永代供養の人気の高さを物語っています。
出典:【第15回】お墓の消費者全国実態調査(2024年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向(いいお墓)
永代供養はいつするかの決まりがない
永代供養においては、霊園や寺院などの墓地への埋葬を義務付ける法律がありますが、時期や期限には決まりがなく、いつするかは自由です。
ただし、仏教は四十九日法要、神道は五十日祭とする忌明け以降に永代供養するのが一般的となっています。
永代供養をする一般的なタイミング

永代供養をおこなう一般的なタイミングには、基本的に3つのパターンがあります。
葬儀後に故人の遺骨を納骨をするとき
死後、永代供養にする最も多いケースは、火葬後に手元にある故人の遺骨を納骨する場合です。
お墓のないご家庭のみならず、故郷などにお墓があっても、住まいの近隣で故人を供養したい方が永代供養を選ぶこともあります。
納骨されている遺骨を整理するとき
お墓は納骨スペースが限られているため、構造的に土へ還せない墓石や納骨堂などでは、古いご先祖様の遺骨から順次、永代供養にして遺骨を整理する必要があります。
遺骨の整理による永代供養は、亡くなった方を納骨する際や、お墓の建て替えやリフォームのタイミングで対処する場合が多いです。
墓じまいや遺骨の引っ越しにより改葬するとき
永代供養は、不要になった墓石を処分する墓じまいや遺骨の引っ越しによる改葬でもおこなわれます。
近年は墓じまいが盛んで、2022年には墓じまいで改葬をした方が過去最高の15万件を超えています。
改葬とは?
改葬とは、遺骨をほかのお墓や永代供養墓へ遺骨を移すことをいい、特定の遺骨だけの改葬も可能です。
たとえば、故郷のお墓から両親の遺骨のみを近場の永代供養墓へ移す場合や、三十三回忌など最後の法要にあたる弔い上げで永代供養にするケースがあります。
生前にお墓の準備をするとき
樹木葬とは樹木や草花などの自然環境が大きな特徴の永代供養墓で、埋葬方法には合祀・集合・個別が永代供養は生前に申し込むことができ、最近は子どもへ負担をかけないよう、生前契約する方が増えています。
墓石のお墓と比べると、永代供養は費用が安価で管理費がかからない永代供養墓もあり、後々のメリットも豊富です。
永代供養をいつするか決める3つの方法
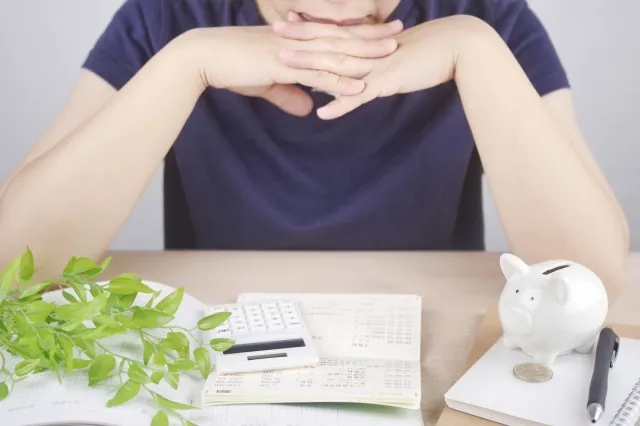
永代供養をいつするかを決めるには3つの方法があるため、家族や永代供養先と相談しながら決めましょう。
法事・法要の日程にあわせる
【四十九日以降の法事・法要】
| 名称 | 日程 |
| 七七日忌 | 49日目 |
| 百箇日 | 100日目 |
| 一周忌 | 満1年 |
| 三回忌 | 満2年 |
| 七回忌 | 満6年 |
| 十三回忌 | 満12年 |
| 十七回忌 | 満17年 |
| 二十三回忌 | 満23年 |
| 二十七回忌 | 満27年 |
| 三十三回忌 | 満33年 |
仏教では七七日忌の四十九日法要で納骨をするのが最良ですが、時期が過ぎている場合は直近の法事・法要の日程に合わせると良いでしょう。
お盆や春彼岸・秋彼岸も供養にふさわしい時期ですが、お墓参りの混雑を避けるには、故人の祥月命日を目安にするのがおすすめです。
家族や親族などの意向にあわせる
家族や親族に要望がある場合は、事情や時期について話し合って決めましょう。
故人への未練から納骨の時期が遅れることや、身寄りのない方や親戚付き合いがない方は火葬後すぐに永代供養するケースもあります。
永代供養の準備が整うタイミングにあわせる
四十九日法要に納骨が間に合わない場合は、準備が整うタイミングで納骨しても問題ありません。
永代供養ではお墓探しや墓石・彫刻の準備に時間がかかる場合や、周囲への説得や手続きなどに時間がかかるケースもあります。
永代供養を早める7つのメリット

永代供養は早いほどメリットがあるため、いつするか迷っている方はぜひご覧になり、早めの納骨をご検討ください。
遺骨の置き場所や供養に困らない
遺骨を自宅で保管すると、置き場所や供養に困る場合や地震などによる被害が不安ですが、早めに永代供養にすれば心配は無用です。
遺骨や骨壷は破損しやすいため、転落などにも注意しなければならず、長々と自宅にあると周囲から不信感を抱かれる場合もあるため注意しましょう。
お墓の費用や維持管理の負担を削減できる
墓じまいは、早めに対処した方がお墓にかかる出費やお手入れの負担を削減しやすいです。
高齢の年金暮らしになると、管理費の支払いや体力的にお墓掃除が負担になるため、墓じまいは健康なうちにすませましょう。
精神的な不安や悩みを早期に解消できる
お墓や遺骨への不安や悩みは精神的な負担になりやすく、自分だけではなく故人や親戚にとっての課題でもあるため、早期に解消しましょう。
とくに寺院墓地の墓じまいでは離檀料などのトラブルが起こらないよう、早いうちからお寺へ相談しておくのがおすすめです。
出典:墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意(国民生活センター)
空きが多い早い段階ほど自由に区画を選べる
永代供養墓は種類によって納骨場所を選択でき、空き区画が多い早い段階ほど選択肢が多く、好みの場所を確保できます。
一例として、マンション型やロッカー型なら目線の高さなど、お参りのしやすい位置が人気です。
生前契約によって相続税対策ができる
お墓や遺骨への不安や悩みは精神的な負担になりやすく、自分だけではなく故人や親戚にとっての課題永代供養は生前契約によって費用を支払っておくことで相続税対策になり、相続人の負担を抑えられます。
永代供養の費用は控除対象にならず、死後は課税対象になるためご注意ください。
家族や親族のリスクを防いで迷惑がかからない
終活により生前契約や墓じまいをしておけば、万一のことがあった際も家族や親族へのリスクを回避でき、迷惑がかからずに安心です。
最新のアンケート調査によると、終活を検討している方のうち「家族に迷惑をかけたくないから」と回答した方は63.9%を占め、家族のための終活が定着しつつあります。
墓じまいや遺骨の引っ越しは時間や手間がかかる
墓じまいや遺骨の引っ越しでは、墓地や石材店への相談や交渉、役所手続きなどに時間がかかる場合があるため、早めに着手するのがおすすめです。
改葬の手続きや永代供養の方法は、後述にてスムーズな手順を解説しますので、ぜひ参考になさってください。
↓永代供養のメリット・デメリットについてくわしく知りたい方はこちら↓
永代供養の種類と費用・特徴

| 種類 | 費用 | 特徴 |
| 合祀・合葬墓 | 約5~30万円 | 複数名の遺骨を混ぜた状態で土に還す |
| 集合墓 | 約20~50万円 | 骨壷などに入った遺骨を保管して一定期間後に合祀 |
| 個別安置墓 | 約50~120万円 | 骨壷などに入った遺骨を仕切られた場所へ保管 |
| 樹木葬 | 約5~100万円 | 樹木や草花の自然環境へ合祀・集合・個別のいずれかで埋葬 |
| 納骨堂 | 約20~150万円 | 室内にある遺骨の安置施設で一定期間後に合祀 |
| 永代供養付き一般墓 | 約100~150万円 | 昔ながらの墓石のお墓で一定期間後に合祀 |
永代供養は種類によって費用が約5~150万円と幅広く、外観や納骨方法、管理費の有無やお参りの仕方なども異なります。
最適な永代供養墓を選ぶためには、事前の現地見学によって、交通アクセスや周辺環境などまでしっかりと確認しましょう。
↓それぞれの永代供養墓の特徴についてくわしく知りたい方はこちら↓
永代供養を速やかに進める手順

二度手間や失敗を防ぎ、永代供養を速やかに進める手順について解説します。
①永代供養や改葬について親族へ相談をして許可を得る
お墓への価値観や考え方は人それぞれ異なり、永代供養や改葬では親族から反対されるケースもあるため、必ず事前に相談して許可を得ます。
②墓じまいや遺骨の引っ越しではお墓の管理者へ相談して許可を得る
墓じまいや遺骨の引っ越しでは、事前に墓地の管理者へ相談をして許可を取り、指定業者の有無や必要な工事内容、手続きについても確認しておくと安心です。
③永代供養墓を探して事前見学のうえ契約する
永代供養墓は資料請求や見積取得のうえ比較検討し、必ず事前見学のうえ利用条件をきちんと確認してから契約しましょう。
④墓じまいや遺骨の引っ越しの準備をする
墓じまいや遺骨の引っ越しでは事前準備が必要なため、次の順序でおこないます。
1.墓じまいでは墓石の解体撤去工事と墓地の返還手続き
2.墓石の工事業者の決定
3.僧侶へ相談して閉眼供養の日程確定
4.改葬手続き
5.閉眼供養後に遺骨の取り出し
改葬の役所手続きをスムーズにおこなう手順
改葬の役所手続きは、次の4つの手順で進めるとスムーズです。
1.既存のお墓を管轄する役所から改葬許可申請書を入手
2.既存のお墓の管理者から埋蔵証明書と改葬承諾書を入手
3.永代供養先から受入証明書を入手
4.役所へ改葬許可申請書と必要書類を提出して改葬許可証を発行
⑤改葬許可証(埋葬許可証)を提出して永代供養墓へ納骨する
最後に、改葬許可証(初めての納骨では火葬後に受け取る埋葬許可証)を提出して永代供養にします。

永代供養の期間で気をつけるべき注意点

永代供養の期間では、気をつけるべき4つの注意点があるため解説します。
永代供養は最終的に合祀されることが多い
遺骨の安置期間が定められている永代供養では、期限を過ぎると一般的に合祀されるため注意しましょう。
期間の開始日を確認する
期間の開始日は契約日のほか、2人以上の複数名を納骨する際は、1人目もしくは最後に納骨した日から起算する場合があるためご注意ください。
年数は単位をしっかりと確認する
安置期間は、1年・3年などの年数と、一周忌・三回忌などの年忌法要のタイミングとがあるため、どちらかの単位に該当するかをきちんと確認しましょう。
延長ができるかどうかを確認する
自分は合祀に抵抗がなくても、家族が嫌がる場合もあるため、世代交代により子孫の意志を尊重できるよう、安置期間は延長可能かどうかを確認しておくと安心です。
合祀しないおすすめの永代供養
他人と遺骨が混ざることに抵抗のある方のため、おすすめの合祀しない永代供養墓についてご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
合祀しない個別安置墓「燈」:70万円~

・宗旨・宗派問わず
・最大15名まで納骨可能
・管理費・寄付金不要
・駅近や駐車場完備で便利な交通アクセス
合祀しない個別安置墓「燈(あかり)」は、対面してお参りできる名板付きの永代供養墓で、大人数が納骨できるため、夫婦両家の永代供養や墓じまいにも最適です。
↓合祀しない個別安置墓「燈」↓

合祀しない樹木葬「永遠なる緑」:39万円~

・宗旨・宗派問わず
・最大6名まで納骨可能
・管理費・寄付金不要
・季節を問わず365日美しい花々が咲く環境
合祀しない樹木葬「永遠なる緑」は、最大6名まで埋葬でき、1年を通して花々が絶えず、気軽にお参りしやすいアットホームな雰囲気が人気です。
↓合祀しない樹木葬「永遠なる緑」↓

まとめ

永代供養をいつするのか決める方法や、早めるメリットについて解説しましたが、いつするか迷う場合は、永代供養先やお付き合いのある宗教者へ相談するのも一つの方法です。
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、全国各地の永代供養墓をご紹介しており、資料請求や現地見学を無料で承っています。
永代供養にする具体的な日取りなど、ご質問やお困りごとも無料で個別相談に対応していますので、どうぞお気軽にお問い合せください。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です