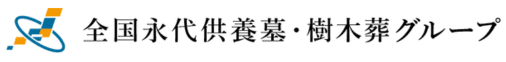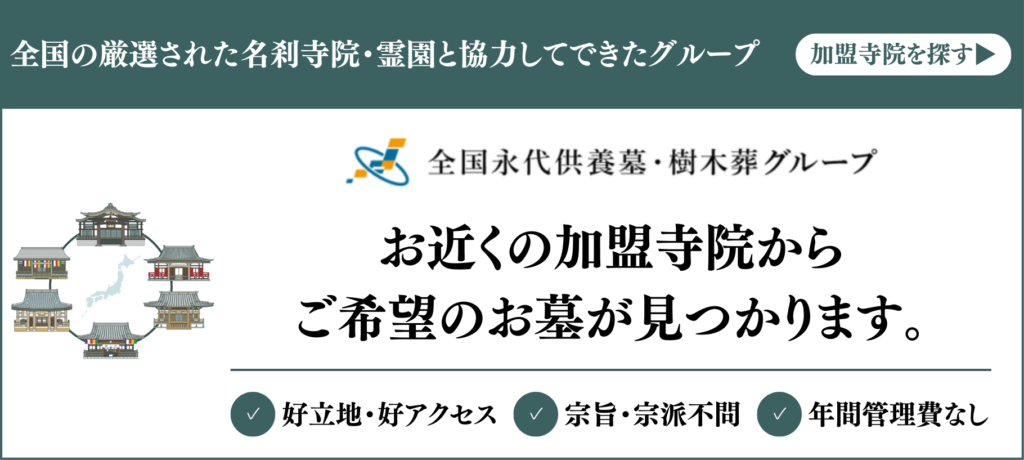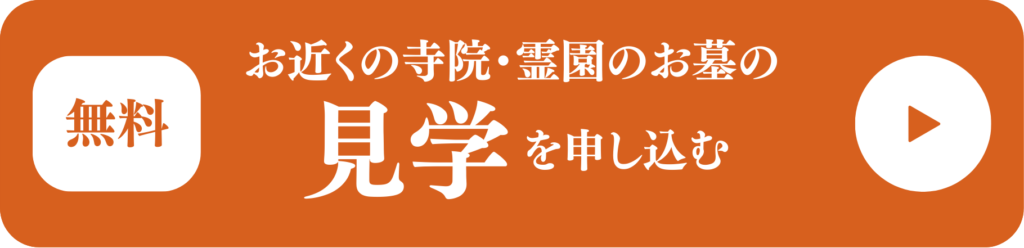墓じまいの補助金制度がある自治体まとめ【2026年・最新版】

墓じまいでは総額30~300万円もの費用が必要になるといわれていますが、実は補助金がもらえる場合があるのをご存知でしょうか?
さらに費用を抑えるコツがあり、最大で数十万円お得にすませることも可能です。
そこで、2026年時点で墓じまいの補助金がある自治体の情報と手続き方法のほか、費用負担の削減方法についてご紹介します。
具体的な費用の内訳や、スムーズに墓じまいを進める手順まで徹底解説しますので、ぜひお役立てください。

墓じまいの補助金制度とは?

墓じまいの補助金制度について、知っておくべき基礎知識を次の3つの順序でご紹介します。
・墓じまいとは?
・墓じまいで補助金がもらえる理由は「無縁仏対策」のため
・墓じまいで補助金がもらえるかどうかは地域の自治体によって異なる
墓じまいとは?
墓じまいとは、不要な墓石を解体撤去して、利用していたお墓の区画を返還することをいいます。
近年、墓じまいによって遺骨を別のお墓へ移す改葬は増加傾向にあり、2022年度には過去最高の15万件を超えたことが発表されました。
というのも、遺骨は法律によって墓地以外の場所へ遺棄することが禁じられているためです。
つまり、墓じまいではお墓の処分のみならず、納骨の措置までおこなう必要があることを理解しておきましょう。
↓墓じまいについてくわしく知りたい方はこちらへ↓
墓じまいで補助金がもらえる理由は「無縁仏対策」のため
墓じまいの補助金をもらえるのには理由があり、墓地を運営する自治体にとって、無縁仏の対策となるほか、返還された墓地を別の利用者へ活用してもらえるためです。
墓石を建立する昔ながらのお墓は放置すると雑草や経年劣化で荒れてしまい、そういった放置されてしまう「無縁仏」が増えていることが社会問題としても認識されています。
参考として、東京都の調査結果によると、公営墓地・納骨堂で無縁仏が発生しているケースは58.2%にも及ぶことが判明しました。
墓じまいで補助金がもらえるかどうかは地域の自治体によって異なる
墓じまいで補助金がもらえるかどうかは、地域の自治体によって異なるため、公営墓地にお墓のある方はぜひ確認してください。
補助金以外にも、自治体によっては助成金や支援制度が設けられているケースもあります。
墓じまいで補助金がもらえる自治体は全国で10ヶ所【2026年】

2026年の最新情報として、墓じまいで補助金がもらえる自治体は、次の10つの公営墓地となっています。
- 宮城県美里町「町屋敷・牛飼共葬墓地」
- 群馬県太田市「八王子山公園墓地」
- 千葉県市川市「市川市霊園」
- 千葉県浦安市「浦安市墓地公園」
- 東京都「都立霊園」
- 静岡県磐田市「市営墓地」
- 大阪府岸和田市「岸和田市墓苑」
- 大阪府泉大津市「泉大津市営墓地・組合墓地」
- 大阪府泉佐野市「泉佐野市公園墓地」
- 岡山県玉野市「玉野市霊園」
自治体による墓じまい支援は、主に以下の3種類に大別されます。
① 原状回復費用の助成
この支援は、墓じまいに際して、墓石の撤去、埋戻し、周辺の整備など、墓地の原状回復に必要な工事の実費を補助するものです。具体的には、撤去作業に伴う重機の使用料や、廃棄物の処理費用、さらには現地の安全確保や環境保全のための整備費用などが給付の対象となります。
② 墓地使用料の返還
この支援は、墓じまいにより墓地が使用されなくなった場合に、前払いされていた墓地使用料の一部または全部を返還する仕組みです。一般的に一度支払われた使用料は返金されません。しかし、この制度が設けられている自治体では申請手続きに基づいて金額が計算され、一部が返金されることがあります。
③ 改葬支援
改葬支援は、遺骨をほかの墓地や納骨堂へ移す際に、必要となる各種手続きや費用の一部を自治体がサポートする制度です。原則として、改葬先は自治体によって指定された場所に限定されます。場合によっては、他人の遺骨と一緒のお墓に納められる「合祀」に限定されます。合祀された遺骨は二度と取り戻すことができません。そのような場合には、サポートを受けるかどうかについて、とくに慎重に検討する必要があります。
宮城県美里町「美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地」
美里町には、②墓地使用料の返還制度があります。
原状回復費用の助成・改葬支援
美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地では、不要になった使用場所を返還する際に、使用許可からの経過年数に応じて永代使用料の一部が還付されます。
町屋敷共葬墓地の場合、使用許可から5年以内は65,000円、10年以内は40,000円、10年以上は20,000円が還付されます。
牛飼共葬墓地の場合、使用許可から5年以内は145,000円、10年以内は90,000円、10年以上は45,000円が還付されます。
また、災害その他相当の事由により必要があると認められる場合は、墓地の永代使用料並びに管理料及びその他の料金が減免されることもあります。
出典:美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例(美里町公式サイト)
群馬県太田市「八王子山公園墓地」
太田市には、①原状回復費用の助成があります。
原状回復費用の助成
太田市八王子山公園墓地での墓石の解体や撤去に必要な工事費を対象に、限度額200,000円まで補助金が支給されます。
千葉県市川市「市川市霊園」
市川市には、①原状回復費用の助成、②墓地使用料の返還、③改葬支援があります。
原状回復費用の助成
墓石の撤去と墓地区画の現状回復費用として、芝生墓地では75,000円、一般墓地では区画の大きさによって210,000~440,000円を限度額として補助金が支給されます。
墓地使用料の返還
使用許可より3年以内に未使用(更地)で墓地を返還した場合、納付した墓地使用料の2分の1、それ以外は納付した墓地使用料の4分の1が返還されます。
改葬支援
市川市霊園合葬式墓地の使用が特例で許可されます。公募以外での生前・遺骨の申込が2体まで可能(1体につき71,000円)で、市外在住者も対象です。
出典:市川市霊園一般墓地返還促進事業(市川市霊園公式サイト)
千葉県浦安市「浦安市墓地公園」
浦安市には、①原状回復費用の助成、③改葬支援があります。
原状回復費用の助成
墓石の撤去と墓地区画の現状回復の工事費用として、最大150,000円の補助金が支給されます。
改葬支援
納骨されている遺骨の改葬先として、合祀施設の提供を無償でおこなっています。
合祀室改葬等許可制度が適用され、納骨されている遺骨の改葬は無償のほか、申込者と配偶者は1人につき、35,000円で生前予約も可能です。
千葉県の墓じまいに関する補助金の詳細はこちらで解説しています。
東京都「都立霊園」
東京都には、③改葬支援制度があります。
改葬支援
東京都では、都立霊園の使用者でお墓の承継者がいない方に限り、遺骨を使用料・年間管理料不要で合葬式墓地に改葬することができます。対象となる都立霊園は以下の通りです。
多磨霊園・小平霊園・八王子霊園・八柱霊園・雑司ヶ谷霊園・青山霊園・谷中霊園・染井霊園・芝生墓地・みたま堂(長期収蔵施設)
以上の方々は、多磨霊園・小平霊園・八柱霊園にある管理費不要の合葬式墓地を無償で利用でき、申込者と配偶者も生前予約ができます。
出典:施設変更制度のご案内について(東京都公園協会公式サイト)
東京都の墓じまいに関する補助金の詳細はこちらで解説しています。
静岡県磐田市「市営霊園」
磐田市には、②墓地使用料の返還制度があります。
墓地使用料の返還
磐田市営霊園(緑ケ丘霊園、八王子霊園、福田霊園、竜愛霊園、駒場霊園、池田霊園、富里霊園、加茂西霊園)では、平成28年4月1日から使用料還付制度が導入されています。
墓所の移転(改葬)や使用見込みがないなどの事由により墓地を返還した場合、使用期間に関係なく、使用許可時に納めた使用料の50%が還付されます。
なお、改葬(お骨の移動)を行う場合は、移し先となる墓地または納骨堂等を決定してから、墓地のある自治体の許可を受ける必要があります(手数料:1件につき300円)。
大阪府岸和田市「岸和田市墓苑」
岸和田市には、②墓地使用料の返還があります。
墓地使用料の返還
岸和田市墓苑では、墓石の解体・撤去後、更地にして返還手続きをおこなう行うことで、使用料の25%(未使用の場合は、1年未満で80%、1年以上で50%)が返還される制度があります。
かつては一部工事が免除される制度がありましたが、現在は玉砂利まですべて撤去が必要なため、ご注意ください。
出典:岸和田市墓苑の墳墓返還による巻石撤去について(岸和田市公式サイト)
大阪府泉大津市「泉大津市営墓地・組合墓地(春日墓地)」
泉大津市には、②墓地使用料の返還があります。
墓地使用料の返還
泉大津市公園墓地では、墓石を撤去のうえ更地にして返還手続きをおこなう行うと、使用開始より15年未満の場合は50%、30年未満の場合は30%の使用料が返還されます。
出典:市営墓地(公園墓地)、組合墓地(春日墓地)に関する各種手続き(泉大津市公式サイト)
なお、春日墓地の場合は、巻石の撤去も必要となります。また、状況により還付の有無が変わるため、還付金額については直接お問い合わせください。
大阪府泉佐野市「泉佐野市公園墓地」
泉佐野市には、②墓地使用料の返還制度があります。
墓地使用料の返還
泉佐野市公園墓地では、区画墓地を返還して合葬式墓地へ移行する場合に、区画墓地使用料の一部が還付され、さらに合葬式墓地の使用料が半額になる支援制度があります。
区画墓地の使用条件と使用許可からの年数に応じて、最大80%の使用料が還付されます。具体的には、未使用で使用許可から1年未満の場合は80%、1年以上経過している場合は50%、墓石を設置・納骨などで使用した後に返還する場合は25%が還付されます。
さらに、合葬式墓地の使用料が通常10万円のところ、区画墓地返還により半額の5万円となります。
なお、この制度は区画墓地を返還して泉佐野市の合葬式墓地へ移行する場合のみが対象となり、他の霊園や寺院へ改葬する場合は還付の対象外となりますのでご注意ください。
出典:泉佐野市公園墓地条例
岡山県玉野市「玉野市霊園」
玉野市には、②墓地使用料の返還があります。
墓地使用料の返還
玉野市霊園では、墓石を撤去のうえ更地にして墓地の返還手続きをすると、使用許可の時期と利用状況によって、10%~100%の還付金が受給できます。
過去の支援事例
宝塚市営長尾山霊園・西山霊園には墓地返還時の還付金制度がありましたが、2023年12月末をもって終了しました。
このように自治体によっては、補助金制度が終了するケースもあります。
予期せぬ事態に困らないためにも、墓じまいの補助金の申請手続きは、墓じまい後、速やかにおこないましょう。墓じまいは計画的かつスムーズにおこなう行うことが重要です。
墓じまいの補助金の手続き方法

申請に必要な書類と手続き
墓じまいの補助金は、墓地を管轄する役所へ、次のような必要書類を提出して申請手続きをおこないます。
【基本的な必要書類】
・墓地の返還届:市町村役場で入手
・補助金の交付申請書:市町村役場で入手
・補助金の交付請求書:市町村役場で入手
・返還に関する書類:市町村役場で入手
・使用者の戸籍謄本:市町村役場で入手
・工事代の見積書及び領収書:工事業者より入手
・工事前後の写真:工事業者へ依頼もしくは自分で撮影
・墓地の使用許可証:墓地の使用者が所有
上記はあくまで一例であり、必要書類は墓地や申請目的によって異なるため、あらかじめ確認のうえ、ご準備ください。
補助金の受給タイミング
自治体によっては、振込口座の通帳の提出が必要な場合もあり、補助金の支払いは基本的に後払いです。いったんは墓じまいにかかる費用の全額を負担することになります。そのため、計画的に資金を準備する必要があります。
墓じまいの補助金以外で費用を抑える5つの方法

墓じまいの補助金以外で、墓じまいにかかる費用を抑える5つの方法をご紹介します。
・墓地の管理者へ事前に必要な工事内容を確認する
・複数の石材店から相見積もりを取得して交渉する
・費用が安い永代供養墓を探す
・お寺へ離檀料やお布施を相談する
・ポイント付与のあるクレジットや、安い金利の墓石ローンや融資を利用する
墓地の管理者へ事前に必要な工事内容を確認する
墓じまいをする際は、事前に墓地の管理者へ必要な工事内容を確認しましょう。
墓地の区画やお墓の状態によっては、外柵と呼ばれる囲い部分の撤去や、土台の基礎部分の工事が不要な場合もあります。
複数の石材店から相見積もりを取得して交渉する
公営墓地にあるお墓を墓じまいする際は、2社以上の石材店から相見積もりを取得すると価格の比較検討がしやすいため、複数の業者へ見積もりを依頼するのがおすすめです。
ただし、寺院墓地や民営霊園では工事のできる指定石材店が定められているケースが多いため、あらかじめ墓地の管理者へ確認しておきましょう。
費用が安い永代供養墓を探す
納骨されている遺骨を永代供養墓へ改葬する際は、あらかじめ利用条件や納骨人数による試算をおこなったうえで、安い永代供養墓を選ぶ方法もあります。
1体なら安価でも、ご先祖様が多いと割高になるケースもあるため、くれぐれも気をつけてください。
永代供養墓は種類も豊富にあり、利用期間や納骨できる人数のほか、後々のお墓参りの方法もさまざまであるため、よりよい永代供養墓を探しましょう。
お寺へ離檀料やお布施を相談する
お寺での墓じまいでは、離檀料や閉眼供養のお布施が必要になります。
あらかじめ、お墓の維持ができなくなってしまう理由や、収入や年金などの事情による悩みを打ち明けておくと、離檀料やお布施の相談をしやすいでしょう。
ポイント付与のあるクレジットや、安い金利の墓石ローンや融資を利用する
墓じまいの費用にお困りの場合は、金利を比較検討のうえ、クレジット払いやローン払いなどの融資を活用するのも1つの方法です。
石材店によってはクレジットカード払いに対応しているケースもあるため、ポイント付与ができるとお得になるほか、墓石ローンに対応しているケースも多くあります。
また、銀行やクレジット会社では、メモリアルローンやフリーローンを提供しているため、相談してみてもよいでしょう。
墓じまいで注意するべきポイント5つ

墓じまいでは、気をつけなければならない注意するべきポイントが5つあります。
・墓じまいを勝手に進めると家族や親族とトラブルになる
・不要な墓地は他人へ売却できない
・遺骨は新たな供養方法を決めなければならない
・墓石を解体撤去して基本的に更地にしなければならない
・寺院墓地は離檀料を求められる場合がある
墓じまいを勝手に進めると家族や親族とトラブルになる
墓じまいをおこなう際は、事前に家族や親族と話し合い、きちんと承諾を得てから取り組むことが大切です。
負担をかけないためという親心だったとしても、子どもの立場ではお墓を継承したいと要望する場合もあれば、合祀墓への改葬に反対する親族がいらっしゃるかもしれません。
後々トラブルにならないよう、墓じまいはあらかじめ家族や親族と相談するようにご注意ください。
不要な墓地は他人へ売却できない
墓地の区画は不要だからといって、他人へ売却することはできず、墓じまいしたあとは、必ず返還しなければなりません。
お墓の土地は永代使用料を支払って、長期的に借りる権利を得ている状態です。他人への転売や貸与はできないため気をつけましょう。
遺骨は新たな供養方法を決めなければならない
墓じまいでは、納骨されている遺骨を取り出す必要があります。また、取り出した遺骨は、基本的に次の3つの方法のいずれかで供養しましょう。
・永代供養:霊園やお寺の永代供養墓で遺骨を管理してもらう
・散骨:海や専用の山林へ遺骨を撒いて土へ還す
・手元供養:自宅で骨壺を安置するか遺骨をアクセサリーなどにする
墓石を解体撤去して基本的に更地にしなければならない
墓じまいでは、墓石を解体撤去するだけではなく、基本的に更地にする必要があるためご注意ください。
未使用の区画でも、墓地は雑草が生えるケースがよくあり、返還する際は除草が必要です。必ずルールを守って墓じまいをしましょう。
寺院墓地は離檀料を求められる場合がある
寺院墓地を墓じまいする際は、お世話になったお寺へ誠意をもって応対するようにしましょう。
離檀料の金額については、基本的にお寺との話し合いになります。
出典:墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意(国民生活センター)
一方的に墓じまいを進めるなど、心ない姿勢はお寺に対して失礼にあたります。トラブルの元となるため、冷静に話し合うようにしましょう。

墓じまいに必要な費用

墓じまいでは、次のような費用が必要となります。あらかじめ相場費用を確認して、予算を把握しておきましょう。
・閉眼供養のお布施
・離檀料
・お墓の解体撤去の工事費用
・行政手続きの費用
別途、改葬先の永代供養墓などの費用も必要となるため、総額を試算しておくと安心です。
閉眼供養のお布施
墓じまいでは、事前にお墓の閉眼供養をおこなうことが一般的で、お布施の相場金額は、3~5万円となっています。
離檀料
寺院墓地の墓じまいでは離檀料が必要です。一般的な離檀料の相場費用は5~20万円となっています。離壇料を求めない寺院もありますが、お寺の格式によってはより高額になる場合もあります。
お墓の解体撤去の工事費用
墓じまいにおける墓石の解体撤去の工事費用は、20~50万円が相場費用です。
面積や墓石の大きさのほか、重機が利用できるかなどの条件によってはさらに高額になるケースもあります。
行政手続きの費用
墓じまいでは、墓地の管理者、墓地を管轄する地域の役所、および改葬先と手続きをおこなう必要があり、手数料は自治体や墓地によっても異なります。
基本的には一基あたり、数百円から数千円前後の費用が必要となるケースが多いです。
↓墓じまいの費用についてくわしく知りたい方はこちらへ↓
墓じまいをスムーズにおこなう10の手順

失敗を防いで、墓じまいをスムーズに進める手順をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
①家族や親族と話し合う
②従来のお墓のお寺や墓地の管理者へ相談する
③遺骨の供養方法や納骨先を決める
④石材店へ見積もり取得をして墓石の解体撤去業者を決める
⑤墓じまいの行政手続きをする
⑥閉眼供養をして遺骨を取り出す
⑦墓石の解体撤去工事をおこなう
⑧墓地の返還手続きをおこなう
⑨新たな供養方法で遺骨の供養をする
⑩墓じまいの補助金の申請手続きをおこなう
①家族や親族と話し合う
墓じまいでは、まず家族や親族としっかりと話し合いましょう。
トラブルを防ぐためには、反対意見にもしっかりと耳を傾けて、どうしたらよいかを確認し、誰もが納得できるようにしておくことが大切です。
②従来のお墓のお寺や墓地の管理者へ相談する
家族や親族と墓じまいの意向が一致したら、お寺や墓地の管理者へ墓じまいの相談をします。
とくに寺院の場合は、あらかじめ継承が難しいことや、費用面でのお困りごとを打ち明けておくと、墓じまいの相談がしやすいです。
墓じまいの意向を伝えたら、手続き方法や具体的に工事するべき内容や指定業者などを確認します。
③遺骨の供養方法や納骨先を決める
墓じまいの手続きでは、改葬先の書類が必要となるため、事前に取り出した遺骨の供養方法や納骨先を決定しましょう。
永代供養墓を探す場合は、必ず事前に現地を見学のうえ、具体的な見積もりを取得して納骨や後々に必要な費用まで確認しておきます。
④石材店へ見積取得をして墓石の解体撤去業者を決める
遺骨の納骨先が決定したら、石材店へ見積もりを取得して、墓石の解体撤去業者を決定します。
石材店や改葬先によっては、遺骨の運搬や新たなお墓への納骨作業までサポートしてもらえるケースも多々あるため、事前に相談しておくとよいでしょう。
⑤墓じまいの行政手続きをする
墓じまいの行政手続きでは改葬の手続きが必要となり、以下の書類を揃えて、墓じまいをする墓地を管轄する役所へ「改葬許可証」を発行してもらいます。
・受入証明書:改葬先の墓地の管理者から入手
・改葬許可申請書:墓じまいする墓地を管轄する役所から入手
・埋葬証明書:墓じまいする墓地の管理者から入手
・改葬承諾書:使用者以外の方が改葬する場合のみ、墓じまいする墓地の管理者から入手
なお、改葬許可証の発行は、一般的に申請手続きから3日から1週間程度かかりますので、スケジュールにはゆとりをもちましょう。
⑥閉眼供養をして遺骨を取り出す
墓石は工事をする前に、あらかじめ読経による閉眼供養をして、遺骨を取り出すことが一般的です。
閉眼供養とは、墓石に宿る魂を抜くための大切な儀式にあたり、家族や親族を集って法事を執りおこなうケースが多く、事前にお付き合いのあるお寺や親族と日程調整しておきます。
⑦墓石の解体撤去工事をおこなう
墓石の解体撤去工事は1日ですむ場合もあれば、整地が必要で数日かかる場合もあるため、あらかじめ日程を確認して工事を着工します。
補助金の申請では、工事前後の写真が必要なケースもあり、事前に伝えておくと業者が代行してくれる場合もありますが、念のため自身で撮影しておくと安心です。
なお、墓石の解体撤去工事は、行政手続きをすませて改葬許可証を入手していなければ着手できません。必ず事前に書類の準備をしておきましょう。
⑧墓地の返還手続きをおこなう
墓じまいの工事が完了したら、墓地へ区画の返還手続きをおこなってください。
この際、墓じまいの補助金の申請手続き方法について、詳細や具体的な金額を確認しておきましょう。
同時に補助金の申請手続きをおこなえる場合もありますが、不備のないようにご注意ください。
⑨新たな供養方法で遺骨の供養をする
取り出した遺骨は、永代供養墓へ納骨するなど、新たな供養方法によって対処します。
なお、改葬許可証は、新たな改葬先へ納骨する際に提出する必要があるため、紛失に注意して手続きをおこなってください。
⑩墓じまいの補助金の申請手続きをおこなう
墓じまいの補助金の申請手続きは、墓じまい後、速やかにおこなってください。自治体によっては、補助金制度が終了するケースもあります。
一例として、宝塚市営長尾山霊園・西山霊園の墓地返還時の還付金制度は、2023年12月末で終了となりました。
予期せぬ事態に困らないためにも、墓じまいは計画的にスムーズにおこなうことが大事です。
まとめ

最新2026年に実施している自治体の墓じまいの補助金制度と、手続きや費用負担を抑える方法をご紹介しましたが、一部の自治体では、助成金などの支援制度が施行されていることあります。
墓じまいのタイミングに迷っている方もいらっしゃると思いますが、お得な制度に該当する方は、ぜひ機会を逃さないようにしましょう。
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、墓じまい後の納骨に最適な樹木葬や、合祀しない永代供養墓をご案内しています。
墓じまいや複数の遺骨の納骨にも対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です