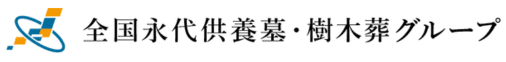水子供養を徹底解説|水子供養の方法や時期とは?永代供養の検討もおすすめ
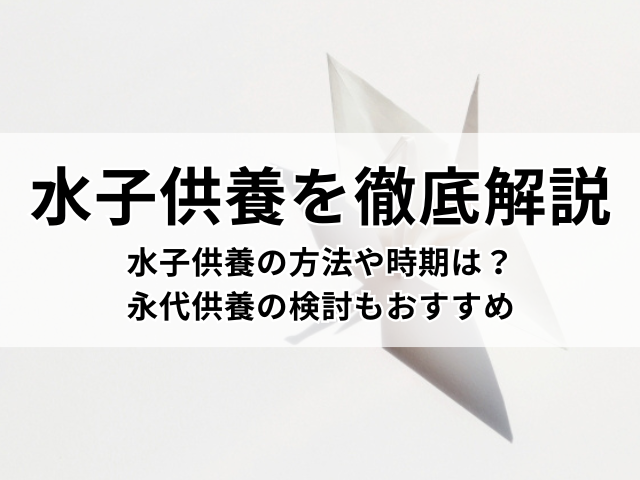
この世に生を受けることなく亡くなった子どもを「水子」と呼びます。
生まれる前に亡くなった子について考えることは、親にとってはデリケートな側面がありますが、供養することで子どもの冥福を祈ることができるだけでなく、親自身のメンタルケアにもつながります。
この記事では、水子供養の時期や供養方法について紹介します。

水子供養とは?

まず初めに「水子供養とは何か」について基本的な要点を解説します。
水子の意味と背景
「水子(みずこ)」とは、流産・死産・人工妊娠中絶などでこの世に生を受けられなかった子どもを指します。水子供養とは、その子の魂を慰め、安らかに成仏できるよう祈るための供養です。
名称の由来は諸説ありますが、昔は亡くなった胎児などを川に流して葬ったからなどという説もあります。
水子供養を行う理由
水子供養を行う理由は人によってさまざまです。
- 子どもの霊を安心させたい
- 自分自身や家族の心を落ち着かせたい
- 仏教的な教えに基づき供養したい
など、宗教的・心理的な側面の両方から供養が行われています。
供養を通じて心の区切りをつけることができ、喪失感を和らげるきっかけにもなります。
水子供養の時期
水子供養に決まった時期はありません。
流産や中絶、死産の後、心が落ち着いたタイミングで供養を行うのが一般的です。
すぐに供養を行う方もいれば、数年経ってから改めて供養を申し込む方もいらっしゃいます。
必ずしも早く供養しなければいけないものではないので、気持ちが落ち着いたタイミングで供養を検討しましょう。
水子供養の方法と費用

次に、実際に水子供養を行う場合の方法や費用について解説します。いくつか種類があるため、ご自身の希望に即した供養方法を選びましょう。
| 供養方法 | 費用 |
| 塔婆供養 | 5千円~2万円 |
| お墓への納骨・水子地蔵の建立 | 数万円~数十万円 |
| 自宅での手元供養 | 5千円~3万円 |
| 永代供養墓へ納骨 | 5万円~30万円 |
塔婆供養を行う
1つ目の方法は、木製の塔婆(とうば)を立てて読経を依頼する方法です。
僧侶に塔婆の作成と読経を依頼し、子どもの冥福を祈ります。
一般的に費用相場は5千円~2万円程度です。
お墓への納骨・水子地蔵を建立する
子どもの遺骨がある場合は先祖代々のお墓へ納骨したり、水子地蔵を建立する方法もあります。
お地蔵様は「子どもを守ってくださる仏様」とされており、多くの寺院で水子地蔵が祀られています。
費用相場はケースによって差があり、数万円~数十万円と幅があります。
自宅での手元供養をする
ご自宅に遺骨や位牌を自宅に安置し、日々手を合わせて供養される方もいらっしゃいます。
近年では、手元供養用の小さな仏壇なども近年では用意されているため、ご検討中の方は仏具店へ相談するとよいでしょう。
手元供養の場合、費用は5千円~3万円ほどが一般的な相場です。
永代供養墓で供養する
永代供養墓を利用する方法も、水子供養を実施するうえでおすすめの方法です。
「ご自身の家庭用に先祖代々のお墓がない場合」や「お墓の継承者がいない場合」「長期的に安心して供養を続けたい場合」は永代供養墓がおすすめです。
永代供養とは、寺院や霊園が永代にわたり供養と管理をしてくれる方法であり、将来にわたって安心して供養をお任せできます。新たにお墓を建立する場合に比べて費用面も安く抑えられる点も特徴であり、おおよその費用相場は5万円~30万円程度です。
また、永代供養墓を選択した場合、将来、自分自身も水子や家族と一緒に眠ることができるという点も特徴であるといえます。
当サイトでは永代供養を実施しているおすすめの寺院・霊園を紹介しています。
お悩みの方は是非一度相談してみてください。

水子供養の流れ

ここからは実際の水子供養の流れを解説します。供養方法によって異なる部分もありますが、基本的な流れは以下のフローで進行します。
申し込みと準備
水子供養を実施する場合のファーストステップは、日程調整と準備物の確認です。
供養を希望する寺院や霊園に連絡し、日程の調整を行います。
この段階で、供養に必要なお布施や持ち物(数珠・供物など)を事前に確認することが重要です。また、戒名を希望する場合はその旨も事前に伝えましょう。
供養当日の流れ
供養当日は本堂や供養塔の前で僧侶による読経が行われます。ご遺族は焼香し、亡き子の冥福を祈ります。寺院によってやや異なりますが、所要時間は30分~1時間程度が一般的です。
供養後にできること
僧侶による供養後は、定期的にお墓参りに訪れたり、お彼岸・お盆に合わせて追加で供養を申し込むこともできます。また、心のケアとして日常的に手を合わせることも大切です。
よくある質問

最後に、水子供養に関するよくある質問にお答えします。
水子供養はいつ行えばよいか?
水子供養には決まった時期はありません。特に親にとってはデリケートな問題であるため、焦らず気持ちの整理がついたタイミングで供養を行いましょう。
お盆やお彼岸に合わせる方もいらっしゃいます。
どのお寺でも水子供養はできるのか?
すべてのお寺で対応しているわけではありません。
基本的な流れとしては、まずは寺院に先祖代々のお墓がある方はそのお寺(菩提寺)に確認し、お墓がない方は新規でお世話になる寺院や霊園を探し、希望にあった寺院を選びます。
菩提寺にお願いする場合も、新規で寺院を探す場合も、事前に「水子供養を行っているか」「供養する場合の費用はいくらか」を確認しましょう。
水子を永代供養で供養したい場合はどうしたらよいか?
水子を永代供養で供養したいとご検討の方は「供養や管理の充実度」「アクセスや費用」などご自身のニーズに応えてくれる寺院や霊園を探しましょう。
当サイトでは、永代供養墓として、個別で納骨できるマンションタイプの「燈」を紹介しています。
水子の永代供養をご希望の方は、是非一度検討してみてください。

まとめ

水子供養は、亡き子の冥福を祈るとともに、遺族自身の心を癒すための大切な儀式です。
方法や時期に決まりはなく、それぞれの事情や気持ちに合わせて選ぶことができます。
将来の供養に不安がある場合は、永代供養を利用することで安心して子どもを見守ることが可能です。
お悩みの方は一度寺院や霊園に相談してみましょう。
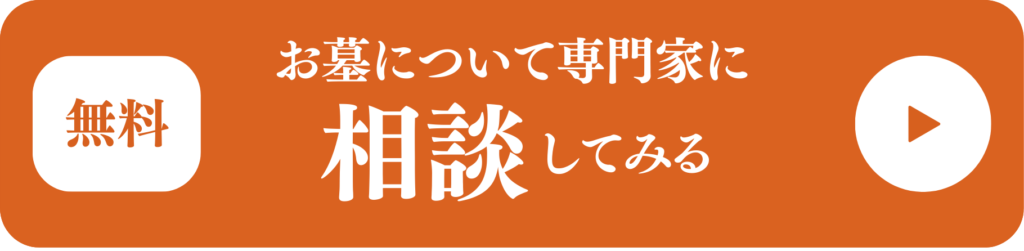
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です