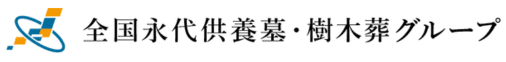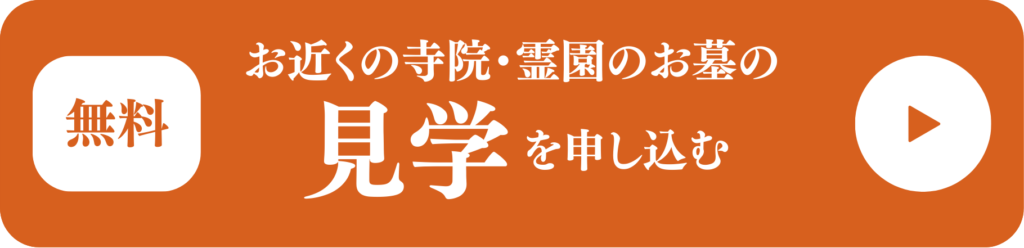墓じまいは何回忌におこなう?お寺にある遺骨を改葬する費用やタイミングについても解説

「墓じまいは何回忌が終わったらしてもいいの?」
「いつ墓じまいをしていいかわからない……」
タイミングがわからず、なかなか墓じまいに取りかかれない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
墓じまいは何回忌でおこなうといった決まりはなく、いつおこなってもよいものです。
この記事では、墓じまいのタイミングに悩む方へ、墓じまいの時期やかかる費用、改葬先の選び方についてくわしく解説します。
家族と親族で適切なタイミングを決定し、納得のいく墓じまいをおこないましょう。

墓じまいは何回忌におこなう?考えられるケース

墓じまいは何回忌におこなうものなのでしょうか。
実は墓じまいは何回忌でおこなうといった決まりはなく、いつおこなっても問題はありません。
一般的には以下のタイミングでおこなうことが多いです。
ひとつずつくわしくみていきましょう。
弔い上げの回忌法要で墓じまいする
はじめに弔い上げの回忌法要で、墓じまいをおこなうケースです。
弔い上げとは、故人へおこなう最後の年忌法要をさします。
弔い上げは一般的には33回忌とされますが、地域や宗派によっては50回忌とすることもあるため、寺院に確認するとよいでしょう。
近年ではそれぞれの事情や家庭環境の変化により、17回忌などで早めに弔い上げする場合もあるようです。
早めの弔い上げを希望する場合は、寺院に連絡し相談のうえ決定しましょう。
そのほかの回忌法要で墓じまいする
墓じまいには決まったタイミングはないため、7回忌、13回忌などの回忌法要で墓じまいすることもあります。
墓じまいは家族や親戚へ同意を得たうえでおこないます。
回忌法要には親族が故人を縁として集まります。そのため、親族に墓じまいの相談がしやすいタイミングであることから、回忌法要で墓じまいをする方が多いようです。
墓じまいができるタイミングは決まっている?

先に述べたように、墓じまいのタイミングに特に決まりはありません。
一般的に弔い上げとされる33回忌が終わってからといわれることもありますが、それ以前の墓じまいも問題なくおこなえます。
近年では後継ぎの有無や管理の負担などの問題により、墓じまいはそれぞれの事情でおこなうようになってきました。
跡継ぎがいない場合、お墓の維持管理ができなくなってしまい、放置された状態になってしまいます。
管理できずにお墓を放置してしまうより、回忌などを気にせずそれぞれの事情にあわせて墓じまいをおこなうのがよいでしょう。
墓じまいについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
墓じまいをしたあとの代表的な納骨先
墓じまい後の納骨先として、現在最も人気なのは永代供養墓と樹木葬です。
永代供養墓と最近注目を集める樹木葬とは、具体的にどのようなお墓なのでしょうか。
こちらでは人気の高い樹木葬のほか、いま話題の永代供養墓を紹介します。
合祀・合葬墓(石材型)

合祀・合葬墓とは、骨壷から遺骨を取り出して、ほかの方々と同じスペースに納骨するお墓です。
共有スペースへ納骨するため個々の区画などはなく、共通の墓標などに手をあわせてお参りをおこないます。
合祀・合葬墓は永代供養墓のなかでも費用は低めですが、ほかの方々と一緒に埋葬されお骨が混ざってしまうため抵抗がある方も少なくありません。
また、一度納骨された遺骨はあとから取り出すことができないため、合祀・合祀墓には慎重な検討が必要です。
集合墓(石材型)

集合墓は、共有スペースに骨壷のまま納骨できるお墓です。
合祀・合祀墓とは違い、遺骨を取り出すことはなく骨壷のまま安置できます。
モニュメントが共用のため、手をあわせる対象がわかりにくくお参りしづらいといった声もあるようです。
そういった意見も踏まえ、自身の希望にあっているかよく考えて選ぶことをおすすめします。
個別安置墓(石材型)

個別安置墓は、仕切られた個室のスペースに納骨されるお墓です。
故人もしくは家族などの複数人でも納骨可能で、マンション型といわれる永代供養墓が最も人気です。
完全な個室に安置されるため手をあわせる対象もわかり、お参りもしやすいといえるでしょう。
個別安置墓は従来のお墓のようにそれぞれの家族ごとに区画があることから、従来のお墓のように家族だけで眠ることができるとして人気があります。

樹木葬

樹木葬は樹木や草花のなかで眠ることができるお墓です。
樹木を墓標とし、太陽の下で大地に還る自然志向のスタイルが近年大きな注目を集めています。
樹木葬は、埋葬の形式がさまざまです。
合祀・合葬型、集合埋葬型、個別埋葬型など、どのような埋葬方法が希望にあっているかよく確認して選ぶ必要があります。
また、埋葬方法により費用も異なるため、予算と希望を総合的に判断し検討しましょう。
納骨堂

納骨堂は屋内の専用スペースに納骨できるお墓です。
機械式、仏壇式、ロッカー式などさまざまな納骨方法があり、近年は交通の便がよい場所にあるビル型の納骨堂も人気です。
一般的に永代供養墓は費用は一括で納め、年間管理料などが発生しないことが多いですが、屋内施設型の納骨堂は、機械の点検費や光熱費などの維持費がかかるため、管理料がかかることが多いです。
検討する際は管理料が発生するかどうか確認しましょう。
永代供養付き一般墓(個人墓)

永代供養墓付き一般墓は、家族ごとの墓石があるお墓に永代供養をつけたものです。
お墓参りの対象が明確なため、手もあわせやすいといえるでしょう。
しかし、個別の区画と墓石があるぶん、価格は高くなります。
また年間管理費がかかるものがほとんどのため、お墓の費用負担を軽減するための改葬先としては不向きな場合は多いようです。
墓じまいしないとどうなる?

継承者がいないお墓を墓じまいしない場合、お墓は無縁墓になってしまいます。
お墓に眠る故人は無縁仏となり、管理されないお墓は荒れていってしまうでしょう。
お墓の所有者や関係者と長期間連絡が取れない場合、寺院や霊園が墓石を撤去する可能性もあります。
墓じまいを何回忌におこなうかについてよくある質問

こちらでは墓じまいを何回忌におこなうかについて、よくある質問を紹介します。
墓じまいをおこなうにあたって知っておきたいこともあわせてまとめました。
墓じまいに役立つよう、ぜひ参考にしてください。
永代供養は何回忌までですか?
永代供養は寺院や霊園が存続する限り続きます。
個別安置墓や個別型の樹木葬の場合、個別安置期間は何回忌までと制限がある場合がほとんどのため、契約時に内容をよく確認しましょう。
永代にわたって合祀にならない永代供養墓・樹木葬が気になった方は、下記をご覧ください。
↓永代にわたって合祀にならないお墓が気になった方はこちら↓
墓じまいは何年でできますか?
墓じまいのタイミングに制限はありません。
継承者の問題や経済的な理由など、墓じまいをおこなう事情はそれぞれです。
家族や親族、墓地管理者に相談のうえ、必要なタイミングで墓じまいをおこないましょう。
墓じまいはいつするのがいいですか?
墓じまいをおこなう時期にも特に決まりはありません。
お墓の所有者の高齢化が進むと、墓じまいも大きな負担になります。
やはり家族や親族と十分に話しあい、墓じまいの時期を決めていきましょう。
「33回忌」とはどういう意味ですか?
33回忌は故人が亡くなってから32年(33年目)経ったときにおこなう、年忌法要です。
仏教の一般的な考えでは、魂が極楽浄土に往生したとされる33回忌は「弔い上げ」とされ、節目の法要になります。
まとめ

墓じまいはいつおこなっても問題ありません。
特に何回忌が終わったら、という決まりはなく、それぞれの事情にあわせておこなってよいものです。
墓じまいにはまず家族や親族への相談が大切です。
かかる費用相場や改葬先のお墓をしっかり調べて、一つひとつ手続きや手配を進めていきましょう。
全国永代供養墓・樹木葬グループでは、全国の古刹・名刹寺院や霊園による永代供養墓のご案内をしております。
墓じまいにともなう質問やお困りごと、改装後の永代供養墓についてもくわしいご案内が可能です。
ご相談はフリーダイヤルまたはお問合せフォームをご利用ください。
経験豊富な専門担当者がくわしくお応えいたします。
この記事の監修者

小原 崇裕
2002年に「NPO法人永代供養推進協会」を設立し代表理事に就任。まだ永代供養が知られていない20年以上前から日本の永代供養墓の普及・推進に努める。年間約1500件の無料仏事相談を受け、エンディングをめぐるお葬式やお墓などへのアドバイスと支援活動に従事。著書に『安心できる永代供養墓の選び方』。シニアライフマネジャー1級。
-
お電話でのお問い合わせ0120-78-7676受付時間 9:00 ~ 17:00
-
メールフォームなら24 時間受付可能です